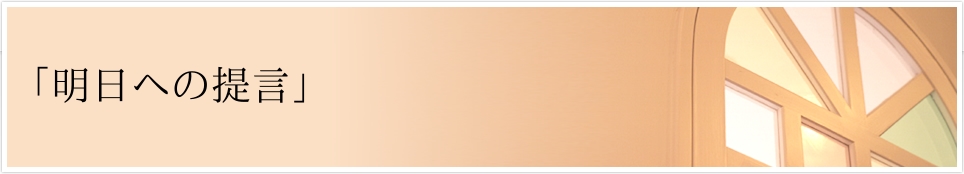井上 雅也(日本大学准教授)
韓国での経験
ソウルオリンピックの少し前、韓国の「農村経済研究院」に1年間留学の機会を与えられた。帰国間近になって、お世話になった研究室の方々数人で送別会を開いてくれた時のこと、崔さんという30代半ばの男性が私にこう言った。「井上さん、私は自分の先祖を恥じている」と。
はて、韓国の人たちは先祖を誇りにしていて、時には自慢するのがむしろ当たり前なのに、「恥じている」とはおかしなことを言うものだと思って、「どうしてですか?」と聞くと、「私の先祖は、豊臣秀吉が朝鮮を侵略した時、祖国を裏切って日本軍の道案内をしてしまった。私は恥じている」と言うのだ。
思いもよらない言葉にびっくりした。いくら何でも400年も前のことで…!
ところがそれだけでは終わらなかった。「井上さんの先祖はそのころ何をしていましたか?」返答のしょうがなかった。私が生まれる10年前の二二六事件でさえ、すでに“歴史”という感覚である。「日本では歴史を学校で習うが、韓国では家で学ぶ」とはこう言うことだった。異文化を肌で感じた一つの経験であった。
ところで、よく「異文化の中に身を置くと日本人であることが自覚される」と言う。しかし“異文化”とは何か。「兄弟は他人の始まり」からすれば家族でさえ“異文化”の住人とも言える。ここでは、異文化を何となくイメージしている”外国”はもとより“隣人”の文化として捉え、私たちがそれと向き合う時に持つべき視点を探ってみたい。