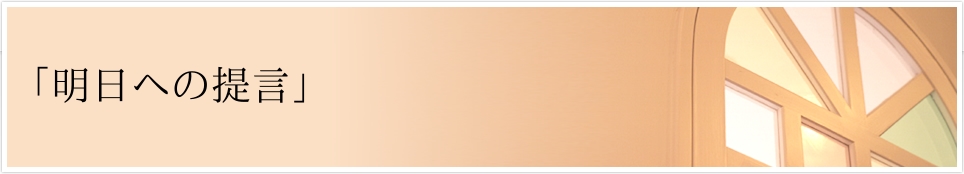島薗 進(東京大学大学院教授)
2011年3月11日の東日本大震災は巨大な津波と原発災害を引き起こし、日本の国土に破壊的な爪痕を残した。2万人近くの死者の追悼において宗教者の参与は欠くことができぬものだった。また、原発災害は経済的な発展に過度の力点を置いたこれまでの生き方の反省をもたらし、大自然への畏敬の念や人間の傲りの自覚など宗教的な価値観に立ち返ることを促しているようだ。
この震災で亡くなった方々の2回目の命日が近づいているが、この度も多くの人々が被災者とともに死者を偲び悲しみを新たにするとともに、困難に満ちた今後の生活をいかに過ごしていくか、またどのように支援していくことができるのか思いを凝らすことだろう。太平洋戦争の終結後、新たな死者の霊を偲び、ともに悲しみを分かち合う葬祭や慰霊の儀礼の意義が、これほど強く納得されたことはなかったかもしれない。死者を慰霊し、死者との交わりを大切にする気持ちを多くの日本人が取り戻したようにも感じられる。
だが、これは必ずしも急なことではなかったのではないか。死者との絆を尊ぶ人々の気持ちを如実に実感させてくれるような経験が近年、比較的多いようだ。2006年の紅白歌合戦では、秋川雅史が「千の風になって」を歌い、その後この歌は大流行した。この歌は死んだ近親者からの呼びかけを歌詞にしたもので、歌い出しは「私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません」というものだ。そういえば、死者の声が聞こえてくるような気がしないだろうか。