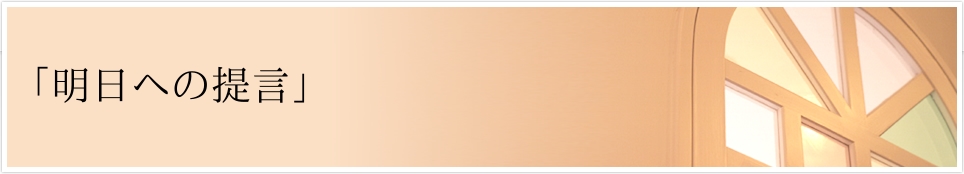島薗 進(東京大学大学院教授)
2011年3月11日の東日本大震災は巨大な津波と原発災害を引き起こし、日本の国土に破壊的な爪痕を残した。2万人近くの死者の追悼において宗教者の参与は欠くことができぬものだった。また、原発災害は経済的な発展に過度の力点を置いたこれまでの生き方の反省をもたらし、大自然への畏敬の念や人間の傲りの自覚など宗教的な価値観に立ち返ることを促しているようだ。
この震災で亡くなった方々の2回目の命日が近づいているが、この度も多くの人々が被災者とともに死者を偲び悲しみを新たにするとともに、困難に満ちた今後の生活をいかに過ごしていくか、またどのように支援していくことができるのか思いを凝らすことだろう。太平洋戦争の終結後、新たな死者の霊を偲び、ともに悲しみを分かち合う葬祭や慰霊の儀礼の意義が、これほど強く納得されたことはなかったかもしれない。死者を慰霊し、死者との交わりを大切にする気持ちを多くの日本人が取り戻したようにも感じられる。
だが、これは必ずしも急なことではなかったのではないか。死者との絆を尊ぶ人々の気持ちを如実に実感させてくれるような経験が近年、比較的多いようだ。2006年の紅白歌合戦では、秋川雅史が「千の風になって」を歌い、その後この歌は大流行した。この歌は死んだ近親者からの呼びかけを歌詞にしたもので、歌い出しは「私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません」というものだ。そういえば、死者の声が聞こえてくるような気がしないだろうか。
街を歩いていたり、家事をしていたりしていて、ふと亡くなった人のことを思い出す。すぐそこに死者がいるように感じることもある。「秋には光になって畑にふりそそぐ。冬はダイヤのようにきらめく雪になる。朝は鳥になってあなたを目覚めさせる。夜は星になってあなたを見守る」。その人はまだ私のすぐ近くに留まっているのではないか。この歌詞にふれて、死んだ配偶者、恋人、子どものことを思い出し、涙ぐむとともに励まされた人は少なくなかったようだ。
2008年には映画「おくりびと」が大ヒットし、国内でいくつも賞をとったが、ついに外国映画部門でアカデミー賞を受賞するに至った。この映画はオーケストラのチェロ奏者を解雇された大悟という名の若い男性が主人公だ。大悟は故郷の空き家に帰って仕事を探す。両親は離婚しており、女手一つで大悟を育てた母は最近、亡くなっている。新聞広告で「旅立ち」に関わる仕事というので面接に出向いたところ、死者を棺に納めることを専門とする葬祭業者だった。社長の人柄にひきつけられた大悟は次第にその仕事を大いにやりがいのあるものと感じるようになる。
大悟の妻の美佳は、大悟が穢れた死体を扱う仕事についたことが気に入らなかった。一度は別れ別れになるが、何とかその仕事の意義を理解するに至る。クライマックスは大悟が子どものときに別れた父の死の知らせを受け、遺骸との対面に赴いた時だ。母を捨て、大悟を捨てた父だが、その後、孤独な生涯を送ったらしくダンボール箱一つの荷物とともに漁港で亡くなっていた。
大悟が自ら父の死体を丁寧に清め、握りしめたこぶしを開こうとしたとき、その手から小さな石ころが転げ落ちてきた。別れる前、大悟と父は河原でそれぞれの思いを託した石ころを交換したことがあった。父は自らの最期に臨んで、その石ころを離さなかったのだ。父子の深い絆は壊れていなかった。確かに父は大悟のことを思い続けていたのだ。
「千の風になって」と「おくりびと」には共通のテーマがある。いとおしい人との切ない別れであり、亡くなったからといってかんたんに断ち切ることができない深い絆だ。涙が涸れるほどの悲しい別れだが、死者への追悼の行為を通して、何とか悲しみを生きる力へと変えようとする人たちがいる。死者に励まされて生きる人たちだ。だが、そこに宗教が見えない。宗教という形にはまっていないので、かえって接しやすいと感じた人が多かったようだ。
しかし、本来、これは宗教が関わる領域だ。宗教は何のためにあるのだろうか。もちろんかんたんに答えられる問いではない。だが、一つの答え方として、人が悲しみから力を生み出す働きを引き出すためにある、とも答えられるのではないか。宗教は人が悲しみを力に変える働きを触発するのだ。
大事な人やものを失うことによる悲しみは重い。愛や絆がもどって来ないということはたえがたく感じられる。だから、悲しみに沈めば元気がなくなる。はた目にも痛々しい方もいる。悲しみは人から力を奪う。ところがよく悲しむことによって、自ずから力がもどり、さらに増してくるということもあるではないか。そして、その時によみがえる力は、悲しみを経ることによって一段と奥深いものになっている。宗教の働きの重要な一面ではないだろうか。
悲しみから生まれる力は柔らかく粘り強く奥深いものだ。身近な他者を喪うということほど、世の無常を痛感させることはない。無常を重んじる仏教はこんな経験と関わりが深い。ゴータマ・ブッダが私たちの親しみ深い模範である一つの理由はここにある。
私がこんなことを考えるきっかけになったのは、比較的年をとってからのことだ。私自身の両親と死別した経験がなければ、考えが先へ進まなかった。死別の悲しみという主題は自分にとって切実な経験がないと考えにくい事柄だ。父が死期が近い病に苦しんでいることを知ったとき、私は法華経に深く親しんだ宮沢賢治の作品を読みふけった。それは私にとって宗教体験に近いものになった。
多くの詩歌と童話を残し、その文学的才能を讃歎する人々が多い賢治だが、生前、華やかな舞台に立ったり、親密な交わりに憩うようなことはなく、37歳でその生涯を閉じた。独身主義を貫き、またその能力にふさわしい社会的地位につくことを受け入れなかったその生涯は、常識的な意味でも寂しいもので悲しみに蔽われていた。
浄土真宗の熱心な信徒であった父との思想的な不一致もあって商家の跡を継ぐことを拒み、他方、個性を花開かせるべく故郷を去ることもできず、結核に苦しみつつ若くして世を去ったこと、最愛の妹であり求道の同志として信頼しあってきた二歳違いのトシが結核で二五歳で世を去ったこと。これらは賢治の悲しみの由来をある程度、説明してくれるものだろう。しかし、賢治の悲しみはこれらふつうの意味での喪失体験によっては説明しきれないような深さと強さをもっている。
よく知られているように詩集『春と修羅』にはトシとの哀切な死別の経験が詩句に結晶させられている。だが、トシとの死別を歌った悲歌の中には、トシとの別れの前から賢治の心の中にわだかまっていた悲しみの響きも込められている。「わたくしのかなしそうな眼をしているのは/わたくしのふたつのこころをみつめてゐるためだ/ああそんなに/悲しく眼をそらしてはいけない」(無声慟哭)。賢治は自らの「ふたつのこころをみつめて」いるために悲しいのだということが示唆されている。トシ自身もそうだったが、賢治は自らの内側に悲しみの源泉を宿していて、そこから悲しみがあふれ出てきてしまうような人間だった。
それは、賢治が自分を「修羅」(阿修羅)と見なしていたことからも知られる。賢治にとって修羅とは、いつも他者との葛藤に苦しんで心晴れず、ふつうの人間の交わりからはずれて薄暗い水中に閉じこめられていると意識しているような存在だ。「まことのことばはうしなはれ/雲はちぎれてそらをとぶ/ああかがやきの四月の底を/はぎしり燃えてゆききする/おれはひとりの修羅なのだ」(春と修羅)。このわけもなくあふれ出るような悲しみ、それは孤独に沈まざるをえないすべての人々の深い悲しみに通じるものなのかもしれない。賢治の悲しみが多くの人々を惹きつける所以だ。
宮沢賢治の悲しみは近親との死別による喪失や、自分の理想を実現できない挫折の悲しみをも含み込んでいる。しかし、それらの個別的な原因だけでは説明できないような何かがあったようだ。だからこそ「あふれるような悲しみ」と言いたくなるような、説明がつかない深い悲しみと感じられるのだ。賢治にとっての仏教は何よりもこの悲しみの入れ物だった。
「ひかりの素足」という作品は、兄の一郎が弟の楢夫とともに、父の働く山小屋から母の待つ麓の家に帰る途中、吹雪に見舞われ、死に直面して、他界にさまよい出ていく経験を描いたものだ。一郎は楢夫をかばい強く抱きしめるが、その後意識を失う。そこから他界にさまよい出た一郎の異次元的な経験が描かれる。一種の臨死体験だ。
その夢のような世界で一郎は楢夫に出会いかけよるが、楢夫は「死んだんだ」といって泣きじゃくる。ふたりは一歩一歩がとがったガラスの上を歩くような苦しみの場所を進んで行く。一郎は鬼に向かって「楢夫は許して下さい」と叫ぶ。そこへ仏のような存在が出て、苦の世界から楽の世界への転換が起こる。一郎は確かに楢夫を守った、しかしそれでも楢夫は助からなかった。やむをえなかったのだ、と辛うじて納得したかのようだ。これは東日本大震災の津波災害の悲しみを彷彿とさせる物語だ。
こうした物語は災害に苦しみ、暴力に傷つけられる悲しみとともに、大事な他者を自ら傷つけていないかという自分を責める意識に耐えられない、そんな繊細な感受性を思い起こさせる。生きていることの条件としてのこうした悲しみを賢治は描き続けた。そのような悲しみへの鋭敏さが読者の心を打つ。
悲しみの原因は自分一人だけの胸にしまっておくしかないような事柄かもしれない。しかし、宮沢賢治の童話作品ではその悲しみが、いわば人類の悲しみに通じるものとして描かれていく。悲しみは皆が分かち合い、ともに耐えていくことができるものではないだろうか。いや、そうなることができれば、いかに重い悲しみも克服できると感じられるのではないだろうか。小さな悲しみは大いなる悲しみに通じている。そうだとすれば、悲しみは大いなる恵みにも通じるのだ。 私なりの勝手な理解だが、宗教は悲しみを入れる器であり、悲しみを力に変える装置だ。この変換は一人一人の心の中でゆっくりと進んでいき、悲しみの働きが自ずから癒しの働きに展開していく。個々人の心で起こるこうした変換を宗教は触発する。そのとき宗教は力をもつ。小さな心の中の大いなる悲しみが大いなる恵みに転ずるのだ。
◆プロフィール◆
島薗 進(しまぞの・すすむ) (1948年生)
東京都生まれ。東京大学文学部・同大学院人文社会系研究科教授。㈶国際宗教研究所長。専攻は近代日本宗教史、比較宗教運動論。
著者に『現代宗教の可能性――オウム真理教と暴力』(岩波書店)、『スピリチュアリティの興隆』(同)、『現代救済宗教論』(青弓社)、『ポストモダンの新宗教』(東京堂出版)、『精神世界のゆくえ』(秋山書店)、『国家神道と日本人』(岩波書店)、『日本人の死生観を読む』(朝日新聞出版)など。
(CANDANA252号より)