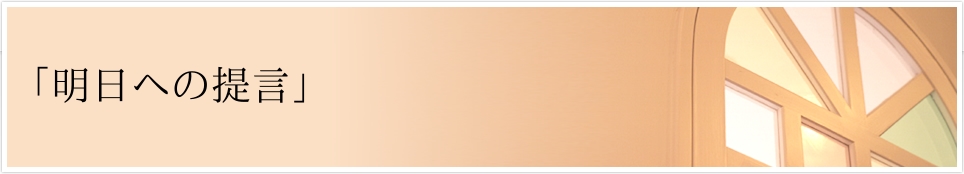杉浦 孝蔵(東京農業大学名誉教授)
はじめに
人々は生活の基本は、衣食住と称しているが、筆者は、食であるとして、「食住衣」と呼んでいる。
日本における食文化の原点は、自然に存在する資源を人々の生活のために生命の安全を確認しながら、安心して美味しく食べるための料理や食事などを工夫してきた地域にある。そして、人々は常に安全な食品を安心して食べたいと願っているが、食を巡る最近の情勢は目まぐるしく、必ずしも安全・安心とは言えない。せっかく和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたのに、これでいいのだろうか。筆者が常々考えていることを2、3提言したい。
日本の食文化の変遷
1 食材の変遷 人類が地球上に誕生し生存するための食材は、生物資源や鉱物資源と推察されるが、食材は生育環境によって異なる。また、人々の食生活も生活環境によって異なる。一方、人口の増加によって、食料の需要も増え食料の大量生産を図るために、生産の安全性・作業の省力などから一部食料の生産場所は、田畑の土地から水耕、砂耕などの非土地に移り、生産時期も従来の季節に応じた栽培から通年栽培に変わった。その結果、食材は人々の健康第一の生産から、市場性の高い物、消費者の好む食材の形、色などの見栄えの生産に変り、さらに、農薬の使用も多くなって食材が持つ本来の味が消失した。
2 食べ方の変遷 食事の取り方も膳を出して座って食べる食べ方は忘れられ、ベッドの中で寝ながら食べたり、乗用車の中で食事をしたり、道を歩きながら食べる傾向が多くなると推測されたが、車の中や歩きながら食べる人が目につくようになった。
また、食べ物も和食から欧米食に変り、調味料も干しいたけ、昆布、鰹節などからバター、ソース、ケチャップ、マヨネーズなどに変った。
さらに、各家庭での食事の取り方も、独りで食べる(孤食)、朝食を抜く(欠食)、家族ばらばらな物を食べる(個食)、好きなものばかり食べる(固食)などに変ったと言う(『朝日新聞』「天声人語」2008)。また、学校給食は、パン、ハンバーガー、ホットドッグ、ピザ、菓子パンなどのファーストフードメニューが多いようである。
このほかに、仕事の疲れか朝食をつくる時間がないのか若い女性のサプリメント依存者が多いと見聞する。最近は男女を問わずに野菜やオオイタドリ、グミ、アシタバなどの山菜を原料としたサプリメントが新聞やテレビのコマーシャルにも見られる。筆者はこのように、薄味、食感の軟らかいものを好んで食べるよりも食材の持つ本来の味覚、食感を楽しむことが健康的な食材の選び方と考える。日大歯学部植田耕一郎教授は、「長生きは唾液」で決まると言う。物を歯で噛むことの重要性を指摘している。0
日本食文化の評価
和食は、新鮮な食材が多く栄養のバランスもよく健康的な食べ物である。そして、自然の美しさや季節感を表現した料理で、人々の生活との関わりが強く、年中行事的である。このような日本人の伝統的な食文化は各国の人々から評価され、2013年12月4日にユネスコ無形文化遺産に登録された。
一方、人間の本能的な感覚である味覚から見ると、西洋は辛・酸・鹹(かん)・甘で、中国はこれに苦味が加わり五味であるが、日本はさらに旨味が加わり六味と言われている。このように和食には西洋や中国の食べ物と異なる味がある。
味覚は甘味、旨味、塩味などの生理的なものと苦味、酸味などの非生理的なものがある。一方、味覚と色彩の関係は、赤、黄、茶は美味しさを増すが、青色系は食欲を失うと言われている。このことから、若い女性は白米をブルーに染めて食べていると言う。
食べ物の嗜好は個人差も多少あるが、食材の本来の味を覚えることであろう。
健康的で好ましい食事とは
美味しく、健康な食事とはいかなる食材をいかに食べるのだろうか。
1 複数の食材を食べる。
1 )日本の長寿村、長寿地区で知られた山梨県上野原町棡原(ゆずりはら)地区を1986年に訪ね、80歳前後の方々に従来の生活状況や食文化を伺った。当地は地利的に都市から隔離された地域であるから産業は炭焼き、養蚕が中心であった。食材はオオムギ、ソバ、アワなどの穀類と野菜でこれに野生の鳥獣や家畜のヤギ乳を飲むなどの自給自足の生活であった。ところが、1954年に地域の待望のバスが開通し、東京都をはじめ都市との交流が一気に始まり都市の生活文化が入ってきた。職場も都市部へ求め従来の野外労働から屋内労働に変わり歩くことより乗り物を利用するようになった。食材も自然食品や繊維食品よりも肉類や加工食品が多くなって急激に生活様式や食文化が変った。その結果、本来ならば一家の柱として生活の中心である後継者が60歳代で早死することが多くなったと古老は嘆いていた。体を常に動かし、穀類を中心に自然食材をとることの重要性が理解される。
当地区の成人病巡回検診を行った古守豊甫医師は、「棡原地区の食事は一見粗食に見えるが粗食ではなく“素食”である。」と評価している。
2 )近藤とし子氏 近藤氏は、多品目を食べることの重要性を生活になじみやすいように言葉で、「マゴタチワヤサシイ」として、マは大豆・豆類、ゴはゴマ・樹の実類、タは卵、チは牛乳、乳製品、ワはワカメなど海藻類、ヤは野菜・果物、サは魚介、肉類、シはシイタケなどのきのこ類、イはいも類を指して多種類の食材から各成分を取ることが健康体をつくることになる、と説いている。
2 旬を食べる 日本の食生活に、いつとなく食べ物は旬の物を食べる習慣があった。すなわち、生き物が発生、熟成し食材として食感、美味しさなどから食べ頃の時期を「旬」とし、この頃に食べる物を旬の物として賞味したのだろう。
深見輝明氏は旬の食材はグルタミン酸の総量が増え、かつ成分のバランスがよくなるからだという。しかし、今日の食材は人工栽培の物が多いから食材の持つ本来の辛味、酸味、苦味、えぐ味、甘味などが無くなっている食べ物が多いと推察される。
植物性食材
1 野菜 植物性食材の代表的な野菜は、農耕地その他で人工的に生産される。農家は作物の生態を考慮し季節に対応し生産してきたが、近年は生産の通年化、生産コスト、多収穫、そして食材の形・色などに主眼をおいた品種改良に努めている。その結果、食材の食感、味覚は従来と異なる。野菜について、朝日新聞のアスパラクラブのアンケートによると(2011年)、好きな野菜はトマト、枝豆、ジャガイモ、ナス、ダイコンなどが上位5に入り、嫌いな野菜はゴーヤ、セロリ、モロヘイヤ、ミョウガ、ウドが上位5に選ばれた。ゴーヤ、セロリ、ミョウガ、ウドは香りが強く、モロヘイヤはぬめりがあるから嫌われると推察する。
2 山菜 日本に生育している山菜は、筆者が農山村の人々を対象にアンケートによって集計した結果約250種になった。また、味の良し悪しを問わず食用可能種をまとめた結果は約600種になった。宮澤文吾、田中長三郎両氏の野生植物図説に約1,000種は食べられると記してある。筆者もさらに調査検討したところ、日本には在来種が約3,500種あると推測し、有毒植物を約1,000種と見なしても残り約2,500種は食べられると推測している。
3 きのこ 日本には野生きのこは4,000~5,000種生育していると言われているが、食用となるのは約300種と推測される。よく食べられているシイタケについて、生と干を比較すると干しいたけが生しいたけよりもカリウム、マグネシウム、ビタミンD、食物繊維が多いが、若い女性は干しいたけの香りが嫌いだから干しいたけは食べないと言う。
動物性食材
自然には多種類の動物が生息している。主な動物をあげると、哺乳類のイノシシ、クマ、シカなど、鳥類のカモ、キジ、ヤマドリなど、魚類のアユ、ウナギ、コイなど、ほかに原野にはヘビ、イナゴ、ハチ、小川にはヒキガエル、サワガニなどが生息している。
農山村の古老はこれらを食材として活用してきたが、最近は農薬の使用や土地開発などによる環境の変化で哺乳類は増えたが、魚類、甲殻類は減っている。
自然食材と筆者の関わり
筆者は、山形県の非農家生れであったから、第二次世界大戦中は農家の手伝いや軍事飛行場(現在の山形空港)の滑走路づくりなどの勤労奉仕に明け暮れた日々であった。これが原因か終戦の時には体調を崩し、どうにか学校には行くが家に帰るとマッサージを受けたり、バスに乗って隣町の病院に行くのが日課であった。さらに、中学から大学2年まで学校が休みに入ると祖母や母の付き添いで東北地方の温泉で湯治を続けた。
当時の湯治場は、春は山菜、夏は川魚、秋はきのこ、木の実などの自然食材が朝市に並ぶので、湯治客はこれら自然食材を副食に用いた。筆者も祖母や母の手料理で季節に応じた自然食材を食べ湯治を続けた。これが筆者と自然食材の関わりである。そして、湯治の余暇には下駄履きで野山に入り、自然に触れたりした。このような行動が筆者の今日の健康の基と理解している。
食文化の今後のあり方
筆者は先人たちの長い歳月にわたる貴重な体験と多くの人々の尊い犠牲の基に構築された食文化を継承することが第一であると考える。そのためには、①農山村と都市の人々の交流が不可欠である。森林、原野や河川などに入り、自然の食材を探して採ることが食材の理解と心身のリフレッシュにもなる。そして、②食文化の体験は幼児期からはじめる。それには家族ぐるみで交流する。この結果、同年齢間の交流と異年齢間の交流もはじまり、相互扶助が生れ、社会生活のあり方を学ぶことになる。さらに、③農山村の美しさ、厳しさの中から生れた食文化を経験豊富な地域の高齢者から学び、体験する。農山村の空き家を活用すれば、長期交流も可能である。
おわりに
ボランティア活動を実施している高齢者は認知症や要介護状態になりにくいと言う。四季を通して自然に触れ、自然食材を食べることの喜びが健康生活の第一歩と考える。ぜひ、日本の食文化の継承を図りたいと念じている。
◆プロフィール◆
杉浦 孝蔵(すぎうら・たかぞう) (1933年生)
山形県生れ。1955年東京農業大学卒業。同年東京農業大学勤務。助手、講師、助教授、教授を経て2002年定年退職。同年東京農業大学名誉教授。この間、大学院専攻指導教授、同専攻主任教授、大学演習林林長、同分収林林長。また中央大学商学部、玉川大学農学部、筑波大学農林学系、静岡大学農学部の非常勤講師。現在、山菜文化研究会会長、一般財団法人木原営林大和事業財団常務理事、新潟県魚沼特使などを兼務。農学博士。
専攻は森林文化、山菜文化、民有林経営。著書に『これからの山菜経営』(全国林業改良普及協会、1984)、『山里の食べもの誌』(創森社、2009)など。論文、報告書約250編。
(CANDANA261号より)