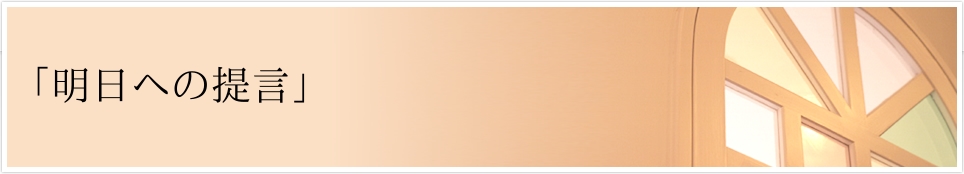眞田 芳憲(中央大学名誉教授)
はじめに
最近マスメディアを賑わしている「イスラーム国家」とは、一体、何者なのでしょうか。単なるテロリストなのか、それともイスラーム主義運動の闘士なのか。
マスメディアを通して報道される情報だけでは、その実像はよく見えてきません。そもそも中東世界に「イスラーム国家」が生まれる背景に何があったのか、イスラーム世界には「イスラーム国家」をはじめ諸過激派の軍事行動の非イスラーム性について厳しい非難があるにもかかわらず、何故にこれらの過激派は依然として激しい武力闘争を展開しているのか、イスラーム過激派組織とイスラームという宗教とは精神的にも政治的にもいかなる関係にあるのか、そもそもイスラーム世界において「テロリスト」と呼ばれる武力勢力の「テロ運動」が激増の一途を辿っているのは何故なのか等々について、オリエンタリズムに毒されない公平から客観的な洞察力のある情報は伝えられていませんし、あったとしても極めて数少ないのが現実ではないでしょうか。
イラク戦争後の紛乱と「イスラーム国」
「イスラーム国」の前身である「イラク・シャームのイスラーム国」(al-daulatu al-’islamiya fi al-‘iraqi wa al-sham:この頭文字をつないで略称「ダーイシュ」)が登場してくるのは2013年4月のことです。2006年に成立し、イラクで活動していた「イラク・イスラーム国(al-daulatu al-‘iraqi al-’islamiya)がシリアに進出してこのように改称、2014年6月末のカリフ国樹立の宣言後は「イスラーム国」(al-daulatu al-’islamiya)という呼称が用いられるようになりました。
「イスラーム国」は、何故にイラクに出現したのでしょうか。これこそ、「イスラーム国」が米国のイラク戦争の産物であることを物語る以外の何物でもないのです。
2015年3月16日、オバマ大統領はインタビューの中で「(イスラーム国は)イラク侵攻の予想外の結果だ」(FOX 通信など)と語り、イラク戦争の失敗を公式に認めました。しかし、こうしたことは開戦当初から予想されていたことで、いまさら「何を言うか」という憤激の念を禁じ得ません。
開戦後すでに、エジプトのムバラク大統領は「この戦争は恐ろしい結果を招くだろう。我々はビンラディンを100人抱え込むのだ。」(朝日新聞2003年8月2日「大統領の戦争5」)と述べていました。ムバラク大統領の予言は的中したどころか、予言で想像した以上の深刻な事態を生み出しています。
「イスラーム国」に支持・忠誠を表明した組織はすでに、中東ではイラク・シリア・レバノン・サウジアラビア・イエメン、アフリカではチュニジア・エジプト・リビア・スーダン・アルジェリア・ナイジェリア、アジアではアフガニスタン・パキスタン・インド・インドネシア・フィリピン等の国々に散在しているのです。
「イスラーム国」はイラクの廃墟の中から噴出した
2003年3月、米国はイラクの大量破壊兵器の開発と所有を理由として──後にこれはでっち上げの偽情報によるものであることが判明──、かつ国連安保理の支持もなしに対イラク戦争を開始し、その2ヵ月後にはサッダム・フセイン政権を瓦解させます。
イラクは、多民族・多部族・多宗教の混在する複合国家であって、サッダム・フセインの専制的な独裁政治によって辛じて国家運営が可能となっていました。それが国家の崩壊によってイラク軍や治安機関も解体、その結果50万を超えるイラク人が失職しました。
それに伴ない戦後、勢力を伸したのが、フセイン政権で弾圧されてきたシーア派とクルド人でした。しかし、旧体制支持者の多かったスンニー派住民が多数を占める地域では反乱が相次ぎ、これに対する米軍を主導とする占領軍の苛烈な武力弾圧が、民間人を含むイラクの人々に大きな惨害を強いることになります。
こうした政治的混乱の中でイラクは暴力氾濫の坩堝と化していきました。強力な統一的政治権力が存在しない混乱した状況の中で、新たな武装勢力が跋扈する基盤が形成され、それが「イスラーム国」の登場となったのです。
擬似国家「イスラーム国」の存立を可能にするもの
「イスラーム国」がイラクからシリア北部にいたる広大な領域を軍事的に制圧し、そこに擬似国家体制を構築し、国家としての統治を可能とするものは何であったのでしょうか。それには幾つかの理由が挙げられますが、ここでは3点のみの言及にとどめておきます。
第1に、「イスラーム国」にはイラク戦争前の旧体制で政治や行政の経験を積んだテクノクラートやイラン・イラク戦争、湾岸戦争、イラク戦争で実戦経験を持ち、アラブ世界の中で最も近代的であった軍事技術・武器庫に精通している旧イラク将兵が参加し、勢力拡大に主導的な役割を果していることです。
第2に、今日のイスラーム世界の諸国家は、19世紀以降、ヨーロッパ列強の植民地主義によって作られた人工国家であるということです。人々の民族のアイデンティティ、そして宗教・文化・伝統のアイデンティティはすべて無視されて作られた国家であるだけに、人々の国家帰属意識が必然的に劣弱とならざるを得ないのです。
第3に、それ故に、イスラーム共同体(ウンマ・イスラミーヤ)こそがイスラーム教徒=ムスリムのアイデンティティを決定する思想的・行動的営みの最終的集結点であるということになります。ムスリムは、いかなる民族、いかなる国家に帰属していても、イスラーム共同体そのものに危機的状況が襲いかかったとき、国家の壁や民族の壁を超えて連帯し、共に自衛のための戦闘に参加することになります。イスラーム世界はもとより、欧米社会からも、金のためであれ、職のためであれ、はたまたイデオロギーのためであれ、実戦の兵士として「イスラーム国家」に糺合するムスリムが存在するのも、まさしくここに理由があるのです。
イスラームの教えと「イスラーム国」
「イスラーム国」は「イスラーム」を称呼しています。イスラームは「イスラーム国」の非人道的な残虐行為を是認するものなのでしょうか。そんなことはありません。イスラームは人間の生命・身体・財産・名誉を確実なものとする具体的な目標をもった平和の教えです。
『クルアーン』には、神の言葉が次のように記されています。「人を殺したもの、地上で悪を働いたという理由もなく人を殺す者は、全人類を殺すのと同じである。人の生命を救う者は、全人類の生命を救ったのと同じである。」(5:32)その上で、イスラームはムスリムに対して侵略戦争を禁止し、自衛戦争のみを認めます。「あなたがたに戦いに挑むものがあれば、アッラーの道のために戦え。だが侵略的であってはならない。本当にアッラーは、侵略者を愛さない。」(2:190)
イスラームとイスラーム共同体を守るための自衛戦争において敵と戦うのが、ジハードです。ジハードは「聖戦」と訳されていますが、それは西洋のオリエンタリズムに毒された訳語であって、本来の意味は「神の道のために奮励努力すること」ということなのです。(『クルアーン』22:78)
ジハードにおけるイスラーム共同体や戦士の行為準則を定めたのが、「スイヤル」(siyar)と呼ばれるイスラームの戦時国際法です。すでに1200年ほど前に、イスラーム世界には現行の「捕虜待遇条約」(1949年)をはじめ、国際人道法に匹敵する戦時国際法が存在していたのです。このスイヤルに従えば、「イスラーム国」による人質の斬首、敵の兵士や敵対した部族民に対する虐殺、無実な民間人を標的とした爆弾テロ、イスラーム化のための戦闘等は、すべて違法であり、イスラーム法上決して許容され得るものではないのです。
それにもかかわらず、イラクやシリアをはじめ、イスラーム世界に「テロ」と呼ばれる暴力が横行、氾濫しているのは何故でしょうか。「テロという言葉は、しばしば強大な権力の側が民族解放運動の価値を失墜させるために用いてきた」(欧州復興開発銀行初代総裁ジャック・アタリ)というこの言葉をよく反芻してみる必要がありましょう。
イスラーム世界では、誰が侵略者で、誰が被侵略者であったのでしょうか。今日、イスラーム諸国で欧米諸国に出兵侵略し、武力行為を行使した国はあるでしょうか。ムスリムの一般大衆から見れば、米軍とその同盟軍こそが侵略者以外の何者でもないのです。従って、彼らの「テロ行為」は米国とその同盟国に対する領土解放と民族解放のための自衛戦争としての「ジハード」以外の何物でもないということになります。
その意味においても、イスラーム世界におけるテロ行為の出発点は、イスラエルの建国とパレスティナの土地の分割を基点として、パレスティナ住民に対する放遂・テロ・殺戮、その後のイスラエルによる国際法無視・国連の決定無視・非人道的なパレスティナ人攻撃と虐殺、度重なるアラブ・イスラエル戦争によるアラブ諸国の勢力劣弱化、欧米諸国のダブルスタンダードの外交政策等にあることを忘れてはなりません。現在イスラーム世界を席巻している「テロ行為」は、まさしくイスラエルとの戦争の中で繁殖した暴力に教化されたテロリズムに震源があるのです。
「イスラーム国」の暴力の連鎖を断ち切る道
それでは、問題解決のためにはどのような努力が必要なのでしょうか。課題が山積している以上、解決策も多様ですが、ここでは5点のみ提示しておきます。
第1に、米国が主導する軍事力による「対テロ戦争」に同調せず、武力によらずに、関係当事者の直接対話に基づく政治的・平和的解決を第一義とすべきです。
第2に、イスラーム世界の権威ある開明かつ公正な宗教者による宗教対話を通して「イスラーム国」による独自のイスラーム解釈と規制の強要に対して反対の立場を明確にすることです。この宗教対話には、国連の主導による場合もあるでしょうし、世界の諸宗教の指導者が同種の宗教対話・宗教協力を行ない、これに支援する場合もありましょう。
第3に、難民・戦争被災者に対する人道支援は、軍事力行使の「侵略」当事国の手を排除し、国際赤十字とかWCRPのような適切な国際人道支援組織の手で行なわねばなりません。
第4に、国の内部の対立や抗争はそこに住む人々が主導する、内部の事情や利益を尊重する民主的・自主的解決を行ない得るような環境を作るべきです。
第5に、最も重要な問題はパレスティナ問題の恒久的解決をめざすことです。武力による解決から対話による解決、国連主導の下で、イスラエルとパレスティナ相互の軍事行動停止の取り決めの実効化に努めるべきです。
◆プロフィール◆
眞田 芳憲(さなだ・よしあき) (1937年生)
新潟県に生まれる。1959年中央大学法学部卒業、1964年中央大学大学院博士課程単位取得満期退学。1968年、中央大学助教授を経て、1974年教授。法学部長(1983―1987)、日本比較法研究所所長(1990―1993)を歴任し、現在、中央大学名誉教授、中華人民共和国政法大学比較法研究所客員教授(終身)、世界宗教者平和会議(WCRP)日本委員会理事および同平和研究所所長。中央学術研究所顧問。
専攻分野:法制史、ローマ法、イスラーム法、比較法文化論。
著書:『イスラーム法の精神』(1985年)、『イスラーム法と国家とムスリムの責任』(1992年)、『平和の課題と宗教」(共著、1992年)、『共生と平和の生き方を求めて』(共著、1999年)、『ローマ法の原理』(共訳、2003年)、『生と死の法文化』(編著、2010年)、『人は人を裁けるか』(2010年)、『東アジア平和共同体の構築と国際社会の役割―「IPCR国際セミナー」からの提言』(監修、2011年)ハッドゥーリ『イスラーム国際法 シャイバーニーのスィヤル』(訳、2013年)など、著書・編著・訳書多数。
(CANDANA262号より)