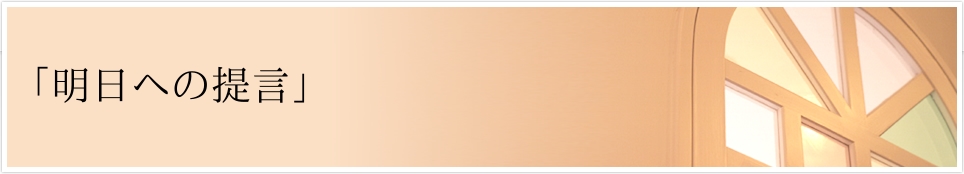諸富 祥彦(明治大学文学部教授)
1.はじめに
私は、「対話」に関心がある。その対話を通して、思考が深まり、人が、よりよく、より自分らしく生きることができるような「対話」に、関心を注いでいる。
そして、自分のしているカウンセリングとか、心理療法といったものが、「思考」が深まり、「自分」が深まっていくような「対話」の典型的なものであると考えている。
一言で、「対話」と言っても、さまざまな種類、さまざまなレベルのものがある。
たとえば、テレビの討論会や、学会でのシンポジウムの対話の多くは、あまり質の良くない対話の代表例である。相手の話を聴いているうちに、自分の中からただ条件反射的に思い浮かんだことを口にしているだけだ。
一方、より質の高い対話も、たしかにある。
その人と話をしているうちに、普段はぼんやりしている自分の考えが明らかになってくる。自分が何をほんとうは考えていて、何をどうしたいのか、話をしているうちに、わかってくる。なんだかその人と話をしていると、一歩前に進めた、停滞していたプロセスが一つ先に展開した、という実感がある。
それが、「ほんものの対話」である。
話そうと思ってあらかじめ準備していたことを理解してもらえた、というだけではない。その人と話をしていると、ひとりでいるときよりも、自分の思考の核心により近づくことができた、という実感がある。ほんとうにわかってもらえていると、人は、自分自身の本質により近づいていくことができるのである。
このような、その対話において、対話参加者ひとりひとりの、自分自身との対話が深まっていくような対話、より深くものを考えることができるようになり、よりよく生きていくことができるような対話、そんな対話の一つのモデルとなりうるのが、現代カウンセリングの礎を築いたカール・ロジャーズのカウンセリングである。