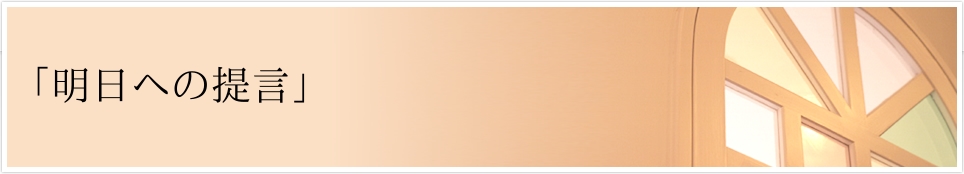宮本 要太郎(関西大学教授)
1.共感にツカレル(疲れる)
この原稿を執筆しているのは2022年6月の初頭だが、2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、開始から100日を経過しても終息がいっこうに見えてこない。この間、テレビでは連日現地からの報道がなされてきている。一般市民を含む多くの犠牲者が、こうして執筆している間にも次々に生み出されていることは、沈痛な思いを引き起こしてやまない。それゆえに、刻々と伝えられる現地の状況に強い関心を抱きながらも、それに触れるのが次第に苦痛に思えてくる。
かかる感覚は、東日本大震災後にかなりの期間にわたって感じたものとよく似ているが、このように、他者の苦難に対して継続的に「共感」することによって自分自身が不安や苦痛を感じることを、心理学や看護学などでは、「共感疲労(compassion fatigue)」と呼んでいる。この概念自体は、1992年にカーラ・ジョインソンが、救急医療に従事する看護師たちの間に、しばしば集中力の減退、知覚の麻痺や無力感、怒りっぽさ、自己満足の欠如などが見られることに関して名づけたもので、「二次受傷」と訳されることもある。
医療や看護をはじめ、一般に支援にかかわる仕事に携わる人々の間で他者への共感に伴ってこのような症状がしばしば見られることは実は古くから知られていて、「燃え尽き症候群」などと呼ばれることもあったが、最近では、この「共感疲労」という用語が徐々に広まっているようである。
もっとも、かかる症状は、対人支援関係の仕事を専門としている人たちだけでなく、報道番組やドキュメンタリー番組を見て強い感動を覚えたり、涙が止まらなくなったりするような、いわば共感能力の高い人々にも同じことが言える。現代ではさらに、テレビだけでなく、誰でも動画を投稿できるYouTubeやTikTokなどのSNS(ソーシャルネットワー
キングサービス)が普及して、悲惨な現地のリアルな情報が際限なくリツイート(再生産)されていくなかで、「共感疲労」はもはや常態化しつつあるのかもしれない(あるいは「共感のインフレーション」)。
2.「共感」とは
この「共感疲労」からは、逃れることはできないのだろうか。諸研究によると、過剰な共感が次第に共感者の心に負担となっていくだけでなく、共感の対象者に対して自分が何もしてあげられないという無力感が、より疲労感を促進するらしい。そのことがストレスとなってうつ状態を引き起こしたり、悲惨な状況にある人たちに共感を示さない人に対して怒りを覚えたりすることも生じてくる。
ところで、そもそも「共感」とはどのようなことを言うのだろうか。私たちが何かに「共感」しているという場合、どのような動きが心身に生じているのだろうか。あるいは「同情」という言葉もあるが、どう違うのだろうか。さらに、「憐み」や「思いやり」などの言葉もある。
私たちが誰か(何か)に「共感する」という場合、実はその内容は一様ではない。たとえば、広い意味での「共感」に類する英語の言葉として、pity、sympathy、empathy、compassionがあり、心理学ではもっぱら、それぞれ「哀れみ」、「同情」、「共感」、「思いやり」と訳されている。いずれも、他者の苦しみや不幸に接した時に生じる心の状態を指すのだが、「哀れみ」では、相手を見下すような気持ちが含まれ、自分を同じような立場において考えることは想定しない。「同情」は、相手のつらさや悲しさを(自分なりに)理解し、気に掛けることを意味するが、「共感」は、自分が同様の経験をしているかのように想像すること(感情移入)で、相手の立場に立つことをより志向している。さらに、「思いやり」は、単に相手の苦しみを自分のものとして受けとめるだけでなく、さらにそれを和らげようとすることを指す。
このように、他者の〈痛み〉に接した時に私たちの心に生じるものには幅がある。これらの違いを考慮すれば、「哀れみ」→「同情」→「共感」→「思いやり」へと、対象に対する思い入れが強まっていることが分かる。
また、「同情」の一般的な特徴として、それを生じさせる対象が限定的であるということと、自然に生じるものであるということの、二つの点が挙げられる。すなわち、私たちが誰かに同情するとき、それに「値する」(と感じられる)ものだけに対して同情するのであり、それは自分の意図と関係なく、内発的に生じてくるものなのである。「同情」にあたる英語のsympathyの語源は、sym(ともに、同時に)+ pathos(パトス=感情)であって、「同じ感情を共有すること」から来ている。このことは、相手によって同情が喚起される度合いが大きく左右されることを意味している。
それに対して「共感」は、対象が抱えている痛みや苦しみを、できるだけ正確に感じ取ろうとする意志によって生み出されるものであり、その気になれば、どのような対象に対しても向けることができる。「共感」にあたるempathy は、em(in =中に)+ pathos(感情)、すなわち文字通り「感情移入」であって、相手が置かれた状況を踏まえた上でその相手の感情や思考の「中に」入っていこうとする意図的な動きであり、したがってこちらはむしろ能力やスキルの一種である。
さらに言えば、「エンパシー(共感)」にも、大きく分けてエモーショナル(感情的)・エンパシーとコグニティヴ(認知的)・エンパシーがあることが認められている。前者は基本的に「他者と同じ感情を感じること」であり、他者の感情や考えに自然に入り込んでいく(同一化しようとする)傾向を含むので、シンパシー(同情)に近い。それに対して後者は、「意図的に自分と他者の違いを担保しながら、他者の視点を取り、自分以外の人間の考え方や感情を推し量る能力」(ブレイディみかこ『他者の靴を履く』)である。エモーショナル・エンパシーが感情に訴える「共感」であるとすれば、コグニティヴ・エンパシーは理性に訴える「共感」と言えるかもしれない。
ただし、実際には、私たちは意識的に「同情」と「共感」を使い分けてはいない。しかし、本当にそれでよいのだろうか。
3.共感にツカレル(憑かれる)
インターネット上では、SNS の広がりもあって、現地の状況を伝える無数の動画や画像があふれているが、それらの中には少なからぬ偽情報やフェイクニュースが含まれているらしい。報道機関は通常、このような情報を使用する前に十分な確認作業を行う(はずだ)が、SNS 上では、早く拡散しようとして、その作業を怠って「共有」ボタンを押してしまう人が後を絶たないという。
このような事態は、ウクライナ情勢に限らず、新型コロナウィルス感染症に関しても、散見された。たとえば、「ワクチンを打つと遺伝子に変化が生じる」「ワクチンにはマイクロチップが入っている」「ワクチンは一部の人間が仕組んだ陰謀である」など、信憑性がかなり疑わしいにも関わらず、広く発信されて共有された情報は少なくない。この、SNS における情報の真偽問題は、それはそれでとても重要だが、本稿では、別の問題に目を向けてみたい。それは、本来あるべき〈共感〉についてである。
春先からこのかた、日本の報道機関は、ロシアがウクライナに一方的に攻め込み、罪のない民間人が多数虐殺され、家を焼かれ、故郷を追われたというストーリーを繰り返し伝えている。それと合わせて、ロシア軍部隊がいかに残虐であり、ウクライナ軍兵士がいかに勇敢であるかが強調され、悲惨な状況に置かれたウクライナ市民への同情を否応なく喚起する。
他方、NATO がウクライナに武器を供与し、それによってロシア軍が苦戦を強いられていることや、国際的な制裁がロシア国内で人々の生活に悪影響を及ぼしていることなどは、淡々と(あるいは冷ややかに)伝えられる。
これらの報道に日夜接していれば、おのずとウクライナ贔屓になるのは必然であろう。もちろん、市民の犠牲が出ていることは疑いようがないし、その犠牲者に対しては、本当に気の毒に思う。日本国内でも、各地で、ウクライナ難民を受け入れる動きが見られ、そのような活動の意義は大きいと感じる。
それでも何だか同調しにくいと感じるのは、勧善懲悪的な枠組みを用いて、軍事的にも経済的にもウクライナを支援し、ロシアに制裁を課すことが、「正義」(道義的)であるかのような前提が、それらの報道に暗黙の裡に共有されているように見えるからである。たとえば、日本の首相は今回の事態について、「国際秩序の根幹を揺るがすものであって断じて容認しがたい」、さらに「(自分に都合の悪いことではすぐに拒否権を行使するロシアや中国を外した)新しい国際秩序の枠組みが必要」などと、繰り返し発言している。「正義」は常に「悪なる者」と「善なる者=被害者」を弁別しようとする。そして、前者に共感することそれ自体が「正義」にもとる行為とされていく。
確かに、戦禍にあえぐ人々のリアルな姿を見れば、そしてそれが無邪気な子どもたちのものであればなおさら、それを見る者は心を動かされ、何とかしてあげたいと思うだろう。そのような思い自体は崇高なものであり、このような心情があればこそ、人間がお互いに助け合って共存していけるのは間違いないだろう。しかし、気をつけたいことは、そのような心の動きが、与えられた情報に対する単なる受動的な反応だけにとどまっているのではないかということ、さらにそのような情報が、誰かによって意図的に操作されている可能性を常に想定しておく必要があるということである。私たちは「気の毒な」人たちの悲惨なシーンを繰り返し見せられることで、そのような「共感」(というよりはむしろ「同情」)に憑りつかれてしまいがちなのである。
そのようにして、自分の感情を自分でうまく制御できない状態が生じる。そうなると、「世間」で通用している「正義」なるものに「同調」して、許しがたいものに対する怒りが生じる。その怒りには、相手に対して「共感」する余地はすでに残されていない。あるいは守るべきものに対して無条件の同情を示す。しかし、それはそれ以外の対象に向けられることはない。同情は常に相手を選ぶが、その選択はたいてい無意識になされるのであって自分の意志でなされているわけではないことを忘れてはならない。自分が「同情」や「哀れみ」や「不正義に対する許しがたい怒り」などにツカレテ(憑かれて)いるかもしれないと気付くことが、認知的共感の出発点であり、そこから生じる感情的共感こそが、自分自身の主体的な感情であるともいえよう。
4.「共感」からコンパッションへ
そのようにして私たちは、感情を自分自身に取り戻すことができる。それは、「共感疲労」を防ぐためにも不可欠である。
ところで、そもそも困っている人や悲しんでいる人に対し、私たちはなぜ心が動かされるのだろうか。自分の接する他者がどのようなことを思っているのか、どのように感じているのかを推し量る能力(エンパシー)は、社会的存在としてのヒト(すなわち人「間」)に本能的に備わっているものであろう。しかし、ただ単に推し量るだけでは、より良い社会を形成するにいたらない。状況を改善するための行動が必要である。その起動力となるのがコンパッションである。
心理学ではもっぱら「思いやり」と訳されることが多いコンパッションだが、ジョアン・ハリファックスは、「コンパッションとは、自分であろうと他者であろうと、その悩みや苦しみを深く理解し、そこから解放されるよう役に立とうとする純粋な思いである」と論じ、また、自分自身や相手と「共にいる力」とも表現している(ジョアン・ハリファックス『Compassion』)。
近年、欧米を中心にコンパッションをめぐる議論が盛んになってきている。とりわけ2001年の同時多発テロ事件以降は、グローバリゼーションの中で改めて宗教におけるコンパッションの普遍的意味が問い直されているのである。もともとコンパッションは、「共に」を意味するcomと「苦しむこと」を意味するpassion から成る概念で「共苦」を意味する。それは他者と「共に苦しむ」ことであり、「他者の痛みを自己のものとする」ことでもある。このようなニュアンスを表現するのに、「思いやり」という訳語では不十分であることは明らかであろう。
むしろ仏教的に言えば、「衆生の困難や苦を見て、何とかしてそれを取り除かんとする強い意志を育む心の態度」であり、「慈悲」ないし「悲」という言葉で表されてきたものである。たとえば『岩波仏教辞典』では「慈悲」について、「仏がすべての衆生に対し、これを生死輪廻の苦から解脱させようとする憐愍(れんみん)の心。智慧と並んで仏教が基本とする徳目。〈慈悲〉は元来、他者に利益や安楽を与える(与楽)いつくしみを意味する〈慈〉と、他者の苦に同情し、これを抜済しようとする(抜苦)思いやりを表す〈悲〉の両語を併挙したもの」と解説する。
重要なことは、他者の苦しみに寄り添い、理解し、共感して、そこからの解放のために努力しようとする態度が、実は他者と同時に、その他者の苦しみを共有する自分自身の救いにも通じるという点である。この意味で、コンパッション(慈悲)こそがエンパシーを正しく方向づけることができるものであり、過剰な共感から生じる「共感疲労」を防ぐものでもある。むしろ「慈悲」は決して過剰となることがない(ハリファックスも、compassionfatigue という表現は不適切であると指摘している)。
「共感疲労」が生じるのは、目の前の苦しむ他者を前にして「私は何をすれば良いのか」を求め過ぎ、同時にそれに思うように応えられない自分の姿に苦しむからであろう。周りのすべての人の苦しみを解消しようとすれば、当然、おのれの無力感に苛まれ、疲弊せざるを得ない。しかしコンパッションは、共苦を通して「私はどう変われば良いか」を問いかけてくる。私たちは無限に変わることができる。その意味で共苦はむしろチャンスでもあるのだ(おそらく菩薩に近づくための)。
◆プロフィール◆
宮本 要太郎(みやもと ようたろう)
宮崎県生まれ。広島大学大学院教育学研究科を経て、筑波大学大学院哲学・思想研究科宗教学・比較思想学専攻博士課程単位取得後退学(在学中シカゴ大学神学校大学院に留学)。博士(文学・筑波大学)、文学修士(筑波大学)、教育学修士(広島大学)。
現在、関西大学文学部総合人文学科比較宗教学専修教授、支縁のまちネットワーク共同代表、関西光澍館運営協議会代表。専攻は宗教学。
著作には「日本宗教における「信心」」(『宗教と倫理』別冊第9号、2021年)、「公共宗教論から公共宗教学へ」(井上克人教授退職記念論文集刊行委員会編『井上克人教授退職記念論文集』、2020年)、「宗教的ケアの理念と現実―「臨床宗教師」の制度化へ―」(木岡伸夫編著『〈縁〉と〈出会い〉の空間へ―都市の風土学12講―』萌書房、2019年)、『闇と光―金光教の信仰から見た現代―』金光教徒社、2018年、「無縁社会における「共苦」「共悲」)のネットワークについて」『関西大学人権問題研究室紀要』第71号、2016年。ほか論文・著書多数。
(『CANDANA』290号より)