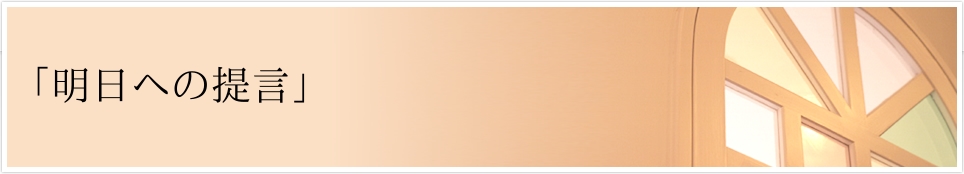伊藤 航多(津田塾大学学芸学部 英語英文学科 准教授)
2021年1月にNetflixで公開された映画『時の面影』(原題The Dig )は、英国の名優キャリー・マリガンとレイフ・ファインズを主要登場人物に配し、実話に基づいて20世紀のイギリス考古学界における最大の発見であるサットン・フーの発掘を描いた歴史ドラマである。
第二次世界大戦の開戦が目前に迫っていた1939年、イングランド南部サフォーク州に位置するサットン・フーの丘で、アングロサクソン族の墳墓が掘り起こされた。中世の初め頃、現在のデンマークやドイツ北部あたりから北海を渡ってブリテン諸島に侵入・移住したアングロサクソン族は、いかにも「海の民」らしく、死者があの世でも船旅を続けると信じていた。そこで、彼らは部族の貴人を葬る際、棺のかわりに一艘の船をこしらえ、そのなかに遺体や副葬品を載せ、丘の上に運んで船ごと土中に埋めたのである。このサットン・フーで発掘された武具や装飾品は、イングランド人の民族的なルーツの一端を象徴する貴重な宝として、現在も大英博物館に飾られている。
この映画の筋立ての一つとして描かれているのは、レイフ・ファインズ演じる地元の考古学者バジル・ブラウンの功績である。彼は高い教育を受けたわけではなかったが、土地勘と経験に秀でた実直な「職人」として発掘を請け負い、地中に埋もれた船を最初に発見した。結局、この国家的な大発見の手柄は、後から発掘に参加した大学や博物館のエリートたちに横取りされていくのだが、じつは郷里に強い愛着をもっていたバジルのようなアマチュアの郷土研究家たちこそが、自国の成り立ち、すなわち歴史や民俗の探求にあたって真に重要な役割を担っていたことが映画をとおして伝わるだろう。
現在では、近所の図書館に行けば郷土史に関するコーナーがふつう設けられているわけで、自分たちの郷里に関心をもつことが特異なようには思われないかもしれない。だが、イギリスでは、郷土の歴史や伝承をめぐる関心が庶民レベルで大きな広がりを見せるようになったのは意外に新しく、じつは19世紀に入ってからのことである。それまでにも各地に土地の由緒を調べて記録するような歴史書は書かれていたが、それらは領主の支配を正当化するためという性格が強く、民衆にはほとんど無縁なものだった。要するに、サットン・フーの発掘を導いたような郷土研究の基盤は、近代化とともに形作られたといっても過言ではないのである。
* * * * *
そもそも19世紀というのは、鉄道・印刷・電信といった技術の発達によって、ヒトやモノ、情報の移動するネットワークが急拡大していった時代である。とりわけイギリスという国は、自由貿易政策やグリニッジ標準時の設定に象徴されるように、世界の平準化を推進する役割を積極的にはたした。そして、イギリスの人々は国内外を旅行したり、新聞のニュースにふれたりすることで、日常の生活圏の外にある世界について見聞を広め、各々が「国家」や「帝国」といった大いなる共同体に帰属しているというアイデンティティを獲得していったのである。
しかし、こうした変化によって、イギリス人の意識がすべて均一に塗りつぶされていったわけではない。さまざまな土地に根ざして暮らしている人々が、「外側の世界」へと組み込まれていくのと同時に、自分たちがやはり他の地域とは異なる「郷土」というローカルな空間に生きてきたことを再認識させられたからである。つまり、世界の距離を縮めるグローバル化に刺激されるようにして、逆説的にではあるが、各々にとって唯一無二の「郷土」が再発見されていったというわけだ。
このような「郷土」の発見にあわせて、19世紀には空前の郷土研究ブームが到来する。それを示すように、イギリスの各地でその地域の歴史や地理、民俗や自然誌について探究する愛好家たちによってクラブが設立された。私が機関誌などの史料調査をおこない活動を確認したイングランドの事例だけでも、19世紀をとおして54の郷土研究団体が誕生している。初めのうち、こうした団体は会員による推薦や投票といった厳しい入会審査を課した。それは入会希望者の学問的な業績を精査するというより、社会的な地位や資産の裏づけがない人々を排除し、エリート的な組織としての品位を保つためのものだった。しかし、この時代をとおして、ちょうど参政権の拡大に歩調をあわせるように、こうしたクラブも入会条件を緩和し、幅広い階層から会員を受け入れるようになっていった。サットン・フーを発掘したバジル・ブラウンのように、独学で歴史や考古学の素養を身につけた庶民が担い手となり、郷土研究の裾野を広げていったのである。
こうした郷土研究団体は、郷土の歴史や伝統文化に関する報告や討論の機会を提供しただけでなく、近隣の名所旧跡への遠足を催し、会員たちの交流を促した。たとえば、マンチェスタを活動拠点としていたランカシャ・チェシャ好古協会(1883年設立)は、日の短い冬季に月例会を開く一方、日照時間が延びる夏季にはストックポート、ボウルトン、ロッチデイルなど近隣の都市やその周辺の史跡を訪れた。1886年の1年間をとおした活動を見ると、合計13カ所への遠足が催され、会員47名によって63題の口頭報告がおこなわれている。
ところで、こうした郷土研究団体で精力的に活動していた主要メンバーのなかには、地元出身ではない者も多く含まれていた。たとえば、ニューカッスル好古協会に所属し、『ニューカッスルとゲイツヘッドの歴史』(全3巻)を執筆した郷土史家リチャード・ウェルフォードは、もともとロンドン出身だったが、イングランド北東部の工業都市ニューカッスルで船会社に勤務することになった。彼の蔵書票には、自画像とともに中世のニューカッスルの風景(川と城郭)が描かれており、この町を「第二の故郷」と定めた郷土史家としての自意識を読み取ることができる。
Newcastle Central Library, Local Studies Collection
彼のように地域の外から来た「よそ者」が主導的な役割をはたしていることも、19世紀のイギリスで広まった郷土研究に見られる特徴である。そして、そこには背景として都市社会の急速な成長が関係していたと考えられる。
* * * * *
19世紀にイギリスでは、産業革命と連動して、農村から都市へと急速に人口移動が進んだ。国勢調査の統計をもとにして人口の少ない村落と人口過密な都会を分け、それらの住民が総人口に占める割合を見ていくと、その比率が19世紀をとおして逆転し、イギリスが農村社会から都市社会へと置き換わっていったことがわかる。先ほど述べたように移動手段の進歩という恩恵もあり、都市はその外部から多くの移住者を渦のように吸い込んで、膨らみ続けた。たとえば、工業都市マンチェスタの人口は、7万人(1801年)から71万人(1911年)に増大している。ただ、このようにして新たに形成されていった都会とは、郷里から引き離されたよそ者たちが群れなす雑多な寄り合い所帯のような空間でもあった。そうした都市部では、貧困や伝染病、犯罪といった問題が浮上する一方で、伝統的に人々を結びつけていた慣習や教会による統制が弱まっていた。そのため、次々に発生する社会問題に対して、まとまりのある一つの共同体として効果的な解決策を打ち出すことが困難になっていったのである。
都市における共同体の結びつきを回復するためには、その拠り所として歴史的な記憶の共有が必要であり、そのために郷土研究への取り組みが促されていくことになる。ここでの郷土研究とは、単純に「古き良き時代」をノスタルジックに懐かしむものではなかった。郷土の歴史や文化を掘り起こし伝えることによって、さまざまな素性をもつ都市住民たちに「第二の故郷」という意識を与え、「共同体の構成員」として社会改良に向き合わせることが急務とされたのである。
そのような目的のために都市自治体によって設立・運営されるようになった施設の一つが、公立図書館だった。今日では想像しにくいかもしれないが、当時の公立図書館は、地元の歴史や自然誌、産業などに関する文献を収集・整理する郷土資料室を最重要部門と位置づけ、一般図書の貸出業務よりもその整備を優先していた。そうした貴重な資料の多くは、篤志をそなえた地元の名望家や市民によって図書館に譲渡されたものである。現在、私のような歴史研究者がイギリスに行って容易に史料調査することができるのも、このように19世紀に諸都市で郷土研究の基盤がしっかり整えられたおかげなのだが、そうした取り組みの根底には、社会が急速に作り変えられていくなかで、共同体を再生しようとする希望が込められていたのである。
* * * * *
最後に、郷土史をめぐる問いかけが、イギリスの社会制度をめぐる政治的な論争にも深く関わっていた点についてふれたい。
イギリスという国は、伝統的にコモン・ローという法体系を遵守し、物事の判断基準として原理よりも慣習を重んじる。つまり、問題を処理する際、抽象的な良し悪しの理屈よりも、過去にどのような先例が積み重ねられてきたのかを参照し、その経験則をふまえて「良識(コモン・センス)」によって判断するというわけだ。そうした社会では当然、政策を決定する際にも歴史的な根拠が問われることになる。19世紀後半のイギリス政界において、争点として浮上してきたのは土地所有をめぐる問題であり、郷土研究の成果がそうした議論の引き合いに出されていったのである。
イギリスというと、世界で最初に産業革命をはたした工業国というイメージを抱きがちだが、18世紀に進んだ大規模な農地開発によって農業大国としても繁栄していた。しかし、1870年代に入って農業の不況が始まり、農村での暮らしが立ち行かなくなっていく。そんななかで、上流階級の地主たちがもはや領地を有効に活用しきれていないにもかかわらず、土地を独り占めし続けている実態を糾弾する声が強まっていった。そして、旧態依然とした土地支配のあり方を見直すよう求める運動が高まっていったのである。
このように世間の風当たりの強い状況のなかで、上流階級の名士たちは、彼らにとって富と権力の源である土地を保持するため、郷土研究を役立てようとした。具体的には、考古学的な測量調査や古文書の編纂事業への支援を積極的におこなった。近代に入ってイギリス各地で開発が進み、地名が改められたり行政区画が整理されたりするなかで、その土地の失われていく姿を記録にとどめようとしたのである。こうした取り組みは、表面的には政治的な争いと無関係だったが、根底には土地の来歴を明らかにすることによって古くからの地主一族の功績や領地との深い結びつきを強調し、土地の支配権を正当化する狙いがあったと考えられる。
一方、こうした保守的な方向性とは対照的に、進歩的な知識人のなかには、郷土研究による発見をとおして社会改革への道筋をつけようとする者も現れた。たとえば、ジョージ・ロレンス・ゴムという人物は、柳田國男の民俗学にも影響を与えたという高名な歴史家・考古学者だったが、本業はロンドン州の行政官であり、彼にとっての郷土研究は単なる個人的趣味ではなく、自治体の政策に直結する取り組みであった。
この当時、ロンドンは大都市につきものの公衆衛生や交通の問題を解決するため、自治体の主導により大がかりな都市改造を進めようとしていた。建物が複雑に密集していた旧市街を取り壊し、広く直線的な道路を敷いて区画を整理しようとしたのである。そのような公共事業を実施するには、自治体が必要な土地を収用できるような権限強化が必要だったが、これも土地の所有権が絡むため、地主の反発を招く厄介な問題であった。
そこでゴムは、自治体による土地収用を正当な権利とする歴史的な根拠を示すため、イギリス各地に伝わる祭礼などの伝統的な共同体の慣習を調べ上げていった。とりわけ彼が注目したのは、大昔のアングロサクソン族の原始的な自治の仕組みである。彼らは部族の政をおこなう際に野外で「ムート」と呼ばれる集会を開き、そこでは男たちが輪になって分け隔てなく合議したという。特に重要視されたのは、生産資源である農用地の分配についての取り決めであった。アングロサクソン族は農用地の多くを部族全体の共有財産としており、集会での話し合いによって定期的に分配し直したと考えられていた。ゴムは、こうした野外集会の習わしを地方自治のルーツと見なした。そして、土地の収用は自治体がいにしえより行使してきた権限であり、民族固有の伝統であると訴えた。このようにして、地主による土地所有の主張を牽制し、公共事業の正当性を裏づける材料として、郷土研究の成果が援用されたのである。
* * * * *
近代歴史学というものが、たとえば「ニホンの歴史」といったタイトルに示されるように「国家」や「国民」を主人公とする大いなる物語を俯瞰的に仕立てていったのに対して、郷土研究の活動はともすれば趣味的でスケールの小さな取り組みのように見られがちだったのではないだろうか。しかし、本稿で述べてきたように、めまぐるしい変化を遂げていた近代イギリス社会では、郷土の歴史や文化をめぐる地べたからの問いかけは、じつは「いま」に跳ね返ってくる切実な問題を映し出していたのである。
ひるがえってみると、現代もコロナ禍は言うにおよばず、グローバル化や気候変動、社会格差の広がりなど大きな変化のただなかにある。このような困難と不確実性に満ちた時代だからこそ、人々の心の拠り所として「ふるさと」への思いはこの先ますます強まっていくだろうし、郷土研究が新たな意味と役割を帯びて世の中に受けとめられていくのではないだろうか。
◆プロフィール◆
伊藤 航多 (いとう こうた)
東京大学文学部西洋史学科を卒業、東京大学大学院総合文化研究科(地域文化研究)修士課程を修了、英国レスター大学大学院にて博士号(歴史学)取得。現在、津田塾大学学芸学部英語英文学科准教授。専門分野は近現代イギリスの社会史、文化史。特に都市における公共文化や規範意識の問題に関心をもって研究している。
著書は伊藤航多「市民文化としての〈郷土研究〉19世紀イングランドの都市における歴史文化とその社会的理念」『史学雑誌』118編10号(2009年)、伊藤航多・佐藤繭香・菅靖子編著『欲ばりな女たち 近現代イギリス女性史 論 集』(彩 流 社、2013 年)、Kota Ito‘, Municipalization of Memorials: Progressive Politics and the Commemoration Schemes of the London County Council, 1889-1907’, London Journal , Vol.42 No.3(2017)など。
(『CANDANA』287号より)