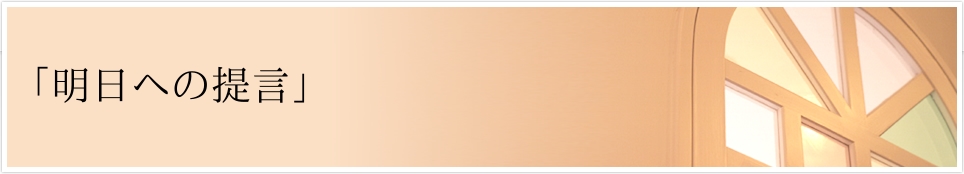岡本 祐子(広島大学名誉教授)
2020年初頭以来ここ1年半、新型コロナウィルス感染症は世界中に蔓延した。わが国においても第1波から現在の第4波までうねりを繰り返し、いまだ収束の兆しは見えない。私たちは、これまでにない閉塞感と不安を経験し、コロナ前とは非常に異なる、制限された対人関係の中での生活を強いられている。このコロナ危機から私たちは、何を学べばよいのであろうか。この1年半の間に、コロナ禍の中で経験したことをもとに、「心を育てる・心をつなぐ」ことの意味について考えてみたい。
1.「生命」というものの意味、亡くなられた方の後ろにあるそれぞれの人生
昨年3~4月、第1波のころの報道は衝撃的であった。外国では、死者が多いので布にくるんだ、良くても棺に入れた何十人もの遺体を並べて埋めていることが、繰り返し報道された。葬儀をしたのだろうかと、初めてこのニュースを見た時に、私は絶句した。わが国でも、亡くなられた方の家族であっても死者に触れることもできない。葬儀もできない。骨壺も直接、受け取れない。ニュースでこれらの映像を見て、いたたまれない気持ちがした。また、昨年2月以降、オリンピック、高校野球など多くの大切な行事が中止や延期になった。
もちろん、感染は防がなくてはならない。日本にコロナウィルスが蔓延するのは防がなくてはならない。しかし、「命」が守られればそれでいいのか。緊急時なのだから、それが最も基本なのだと、専門家も政府も言う。
第1波の昨年3月に、私がもっと重大なことが起こっていると感じたのは、「コロナウィルス感染拡大を防ぐためには、仕方がない」と、多くの人々が「簡単に」そう考えてしまうことであった。亡くなった人の人生、一生に一度しかないその行事ができなくなったこと、その人と自分との関わりに思いをいたすことをしない。それは、他者へのリスペクト、特に亡くなられた方へのリスペクトがなくなったことを意味する。亡くなった方への敬意は、どの文化でも葬儀・告別式という形で、大切にされてきた。死者に対して敬意を払うことは、自分の社会が大切にしてきたものを守ること、自分の社会の過去、歴史を考えることである。生きてきた人の重みに敬意を払わなければ、私たちの社会は、ただ「現在」だけという、薄っぺらな社会になってしまう。せかせかとその場をやり過ごしてしまうという心の在り方は避けたいものだと思う。
2.社会と「普通の関わり」が持てない人の体験世界の共有
このコロナ危機を経験して、私たちは突如として、自分たちの生活の流れを中断され、時には、大事な人から切り離され、いつ再会できるか、もう一度会えるかどうかもわからない、私たちの生命や関係性そのものが、実は相当脆弱なものである、という強烈な体験をした。私が体レベルの感覚として感じたのは、コロナ以前には、普段の生活では少し遠い存在であった「病気の人」だけが心の中で体験してきた現実世界に、実は自分自身も居るということである。未来への不確定さ、制約の多い生活、社会的関係が乏しくなること、仕事上の関わりも限られること、死ぬことの不安など。病気の人、障害を持った人、高齢者、犯罪被害者など「社会」と通常の関わりが持てない人々が体験していることは、どんなことなのか、私も体験した。こういう体験を共有できたことは、本当に大切なことだと思われる。
心に関心を持つ人、当事者という相手に向き合う関係性の中で仕事や生活をしている人は、相手に向き合うとは、どういうまなざし、態度、言葉が必須なのかに対して、感性を磨かなくてはならない。この本質的なところが、私たち一人ひとりの「言葉と行動」で表せるなら、そしてこれが、これからのコロナ時代の新しい関係性の中に生きていけば、それはすばらしいことである。つまり、危機や痛み、疎外感を抱いた当事者に対して、それに気づいていることを、本人と言葉を交わし、その気持ちを分かち合うことが、その後の人生を生きていくうえで、本質的な活力になる。
言い換えれば、当事者の気持ちに気づいていることを、言葉で伝えるということは、相手に対して自分がその「鏡」になる、「鏡」になることで相手に見える形で伝える、支えることを意味する。これらはこれまで、心理臨床の場で培われてきたカウンセリングやコミュニケーションの在り方であるが、このような「言葉と行動」が、コロナ危機という現在の社会においても非常に大きな力になるのである。そしてこれは、心理学の専門家でなくてもだれでもできる基本的なことである。
3.「人と会う、対面する」ことの意味
コロナ危機によって、現在もなお、私たちは対面で人と会うことを厳しく制限されている。それを補うために、オンラインの技術は、職場や学校に目覚ましく広がり、私たちの多くはその技術を使えるようになった。ZOOM会議システムなどは、マネジメントレベルでは良いシステムで、このオンライン技術が発達していたおかげで、私たちは組織や社会の機能的な崩壊を免れた。
しかし私は、「対面で相手と会う」ことは、人間にとって本質的に重要な意味を持つと考えている。「人と会う」ことは、言葉で伝える、言葉でわかり合う、その内容はもちろん重要である。しかしながら、私たちが対面でわかり合うものは、言葉で伝えられる内容とともに、「空気」「表情」「しぐさ」という非言語的なものとともに、「気」という、自分から発する力・活力、相手に対面しやり取りする中で直感的にわかる域が重要な要素として含まれている。これがどの程度、相手に伝わるかが、人と会う成果を決めるといってもよい。大学の講義やゼミなどはその典型である。言葉は、もちろん大事であるが、「会えない」状況でオンラインに乗った言葉は、その人が伝えたいことのほんの一部でしかない。相手の受け取り方も、言葉だけでは本当に真意が伝わらない。相手と「会う」「対面する」ことは、
① お互いを見て、その場で反応する。気持ちをわかり合う。
② 相手と主体的に関わり合う。そして、
③ 相手と向き合うことによって、自分自身が見える、自分ももっと力が出せる。
という意味で、人間の本質的な営みである。
コロナ危機の状況下で、オンライン技術はマネジメントレベルでは、すばらしい効力を発揮している。しかし、マネジメントを超えた域ではどうだろうか。人育て、関係つくりのような領域では、うまくいっているのだろうか。新しい信頼ある関係性は生まれているのだろうか。
コロナが収束した後も、このオンラインでの関わりはずっと持続していくであろう。こういう状況の中で私たちは、心を育てる、心をケアする営みを続けていかなければならない。そのためには、注意深くオンラインとオフライン(対面)を行き来する世界を作っていく必要がある。
IT技術を身につけ、活用することで、「会えない」弊害を可能な限り少なく、しかし、育てる、関係性を創るという、マネジメントを超えたレベルを見逃さないで、どうつないでいくか。私は、オフライン、つまり対面で会うことの意味と価値を見逃さないためには、自分の感性と活力が必須だと考えている。この両方の世界を自分のものにして、両者を行きつ戻りつする。この「自分のものにする」とは、両方の世界の意義を知り、その意味を生きる、ということである。
4.他者と関わり合う営みの歴史
私たちは、これまでの歴史の中で、他者とどのようにわかり合ってきたのであろうか。人間や社会・文化にとって重要な知見や知恵をどのように伝えてきたのだろうか。大別すると、それは次の3つの段階があった。
1.口伝の時代:対面で場を共有し、その「場」で伝える。
2.書いたもの・文字で伝える時代
3.電子データ、デジタル技術で伝える時代
現代の私たちの世代は、2.紙媒体に記録された文字によって、学習・勉強・研究する時代が長く続いた。これによって、時代や世代を超えて知識の伝達・継承が可能になった。しかし、それらを自分の血肉にするためには、主体的に理解すること、集中して読み考える長い時間が必須である。
1990年代から3.デジタル時代へ移行した。21世紀になって、それはさらに進化し、瞬時に誰でも情報を送信・受信できる社会が到来した。すばらしい技術であるが、このスピードと人間の心のキャパシティは、ともすればズレるという危険もはらんでいる。
一方、1.口伝の世界は、現代ではごく一部の世界に存続するのみとなった。伝統的芸術・文化、宗教、特に禅の世界などは、現代も口伝が重要な意味を持っている。書いたものだけでは伝わらない。その場を共にし、「生きた師匠を見て、盗み取って自分の力にする」という世界である。しかし、このような世界は、今日もなお、私たちの生活と心を支える重要な意味を持っている。
このような世界では、誰に出会ったかが、その人の専門家人生にとって決定的な意味を持っていた。現代においてもそうである。教育、中でも専門家になるための教育も、つい最近まではそういう世界だった。
その意味で、定年退職を迎えるまでの広島大学での私の仕事、つまり教育、次世代の専門家の育成と研究は、最後までこの口伝、「気」の伝達の中で、人間的土台を理解し合い、その土台の上に、専門家(私のゼミの場合、発達臨床心理学の研究者、心理臨床家)として資質を育てるという営みであった。それを長きにわたって実践し、多くの門下生が専門家として育ってくれたことを、心からうれしく思っている。
5.コロナ危機から何を学ぶか-「危機を経験する」ことの意味-
1)他者の“鏡”となる出会いとコミュニケーション
昨今のコロナ危機の中で、人類と感染症の歴史に関する多くの書物が改めて注目されたり、新しく刊行されたりしている。村上陽一郎(1983)『ぺスト大流行』(岩波新書)には、感染症によって人口が激減し、生き延びた人々が次の新しい世界を再建していったこと、人類はこの繰り返しであったことがわかりやすく解説されている。私たちの人類の歴史を通じて、「生き延びる」ことが、どれだけ大変なことであったか。世界と歴史を見る目が変わる思いがしたものである。
コロナ危機体験から、私たちは何に気づけばよいのか。その最も大切なことの一つは、相手・他者の“鏡”となる出会いとコミュニケーションではないであろうか。簡単に会えない今日、何とか相手に見える、聞こえる「言葉と行動で伝える」ことは、非常に大切である。
コロナ時代の新世界で、この人々とつながり合えるための認識・行動・方法を、一人一人が持てれば、ペストやハンセン病が蔓延した時代、戦争を経験した時代から、さらに時を経た現代の私たちの心の成熟性として、コロナ危機から学んだことと言えるかもしれない。
2)経験をつなぐ
私たちは、コロナ前とコロナ後の2つの世界を生きなければならない。コロナ後の世界は激変すると言われている。IT技術を身に着けることは必須であり、人間関係の持ち方も大きく変わる、それに適応していかなければならない。しかしながら、2020年以前、コロナ流行前の「自分」、つまり、私たちがこれまで積み上げてきた経験を捨て去り、新しい様式に乗り換えるというスタンスでよいのだろうか。成熟した人間と社会は、「経験をつなぐ」ことができてこそだと考える。
それでは、薄っぺらな人間・社会にならないために、コロナ前に培った「経験」をコロナ時代にどのようにつなげていけばよいのだろうか。
3)危機体験と心の発達
私は、臨床心理学を専門とし、青年期以来、アイデンティティの生涯発達と危機について研究してきた。青年期に一応のところ獲得されたアイデンティティ(=自分は何者で、どう生きていくのか)はその後の人生の中で、危機に遭遇する毎に問い直され組み直されて深化していくことがわかってきた。「人生の危機」は、青年期、中年期、現役引退期という人生の節目だけでなく、予期せぬ人生の危機も、数えきれないほど存在する。人生半ばで大病を患うこと、障害を持つこと、愛する人を失うことなど。特に、危機を経験する前の自分には戻れない絶望や喪失から回復していくそのプロセスから、危機前の自分とこれからの自分をつなげられることが、再び主体的な生き方を取り戻す力になることがわかってきた。つまり、危機体験を自分の人生に組み込みながら、それとともに生きることである。私は、この転換こそ、「心の成長・発達」であると考え、そのプロセス、メカニズムを研究してきた。
2つの世界を行きつ戻りつし、両方の世界を自分のものにする。2つの世界を生きることが、これから生き延びていくためには、必須ではないであろうか。そのためには、
1. 自分の中に2つの磁極をもつ。自分の中に、複数の視点をもつ。磁石の極を2つもつ。それを引きあいながら、適した方向を見出していく。
2. 危機を踏みこたえる力を、自分および、自分と他者との関係性の中にもつ。
このことが、危機の時代を生き延びるために肝要であると、私は考えている。
6.コロナ禍にこそ「心の分かち合い」を
しかしながら、自分の力だけでこの危機を乗り越えるのは相当厳しい。長引くコロナ危機で、多くの人々が心の通ったコミュニケーションが持てず、生きづらさを感じている。こういう日々にこそ、人と人との関係性をより良いものにする「努力」が大切であろう。悩みやストレスを抱え込んで孤立している人も少なくない。そういう人に対して、周囲にいる家族や知人が気づき、声をかけることができるかどうか。そして説教や励ましではなく、その人の気持ちの「聴き役」になれるかどうかが大切である。うまく聞くことができなければ、カウンセリングの専門家につなぐことも大きな助けになる。気持ちを分かち合える人の存在は、心強い。コロナ禍にあって、対面での心の交流が難しい今日であっても、他者との「心の分かち合い」を大切にしたいと願っているこの頃である。
◆プロフィール◆
岡本 祐子(おかもと ゆうこ)
広島県生まれ。広島大学名誉教授、HICP東広島心理臨床研究室代表、教育学博士、公認心理師・臨床心理士。
専門は、臨床心理学、生涯発達心理学。青年期以来、中年期の発達と危機を中心とした成人期のアイデンティティの発達臨床的研究に携わる。並行して、力動的心理療法のオリエンテーションをもつ臨床心理士として、子どもから高齢者までのカウンセリング・心理療法を実践してきた。2012年8月、これまでのアイデンティティ研究・ライフサイクル研究の成果が国際的に認められ、アメリカ合衆国Austen Riggs Center よりEriksonScholar の称号を授与された。
主著『プロフェッションの生成と世代継承』、『世代継承性研究の展望』、『成人発達臨床心理学ハンドブック』(以上、ナカニシヤ出版)、『アイデンティティ生涯発達論の射程』(ミネルヴァ書房)、『女性の生涯発達とアイデンティティ』(北大路書房)など多数。
(『CANDANA』286号より)