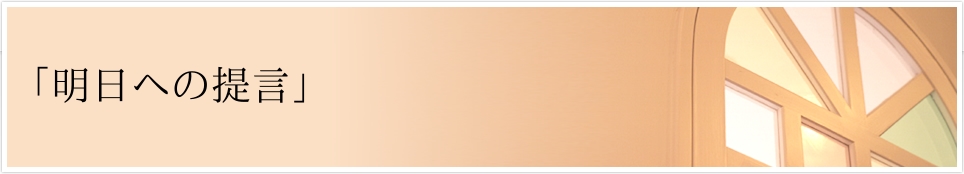手島 勲矢(京都大学文学部非常勤講師)
今年2023年は、ユダヤ思想家ブーバーの世界的な代表作『我と汝』(1923年)が出版されて、100年の節目に当たる。戦後の日本でも、ひと時ブーバー・ブームがあり、彼の著作集がみすず書房から出版されたり、岩波文庫にも『我と汝』が加えられたりしたので、その頃を知る読者には、一度は耳にしたことのある、懐かしい書名ではないかと思う。
実は、縁があって、僕もマルティン・ブーバーの名前は小さい頃から知っていた。それは、私の父(手島郁郎)がエルサレムのブーバーの自宅で彼と面会していたからである(1963年)。父は、その時の思い出を文字にしている(『生命の光』No.153)。その父との関係は、ブーバーの往復書簡集(G. Schaeder,Martin Buber Briefwechsel, p.576-577)にも認められるので、今年は父がブーバーと面会した60年目にも当たる。ある種の感慨を覚えながら、経緯を述べた父の報告記のページをめくると、ブーバーと面会する父の写真に加えて、そこには老齢のブーバーが泣いている一枚のスナップも載っている(片岡鬨夫氏の撮影)。
その写真は、小さい頃から僕の心にはとても焼き付いている一枚なのだが、世界的な哲学者と言われるブーバーの涙のわけは、報告記に書かれている。どうやら父は、ブーバー宅の安息日ディナーに招待されていたらしいのだが、にもかかわらず父が尊敬する親友の訃報を聞いて急遽予定を変えて、安息日を待たずに帰国することになった。その旨を伝えに行ったところ、「どうして帰国するのか、なぜわずか一日を伸ばせないのか、昨日やってきて、もう帰るとは! その人が死んだのなら、帰っても、もう会えぬじゃないか」とブーバー翁が非常に残念がったという。その言葉に、父は「この方はいわば養父の如き人である、この最愛の人を失って、私は地球が空虚(empty)のように感ぜられる」と応じた。そのやり取りの中で、ブーバー翁は泣かれた。その風景の一枚であったようだ。
その時のことを父は、「愛するものを失って、うなだれ悲しんでいる私を見て、共に涙されたのがブーバー先生でした・・・この多感な哲人ブーバーは共感なさるのでした」と記録している。僕には、その多感な人ブーバーの涙の姿が、ずっと不思議で謎な風景で、ある意味、その一枚のフォト・スナップは、今見ても衝撃的である。その気分は、多分、何度か『我と汝』を読もうとしても、最初の数行の言葉「世界は人間にとっては、人間の二重の態度に応じて二重である。人間の態度は、人間が語りうる根元語(Grundwort)が二つであることに応じて二重である」(田口義弘訳p.5)の意味がわからない読書経験によっても増幅されていて、冷徹な理性の議論スタイルのイメージに、彼の涙はそぐわない、という僕の勝手な思い込みでもあった。
だが、近年イスラエルで、ドイツ語の原著(Ich und Du)がヘブライ語に訳し直されたというので、その新訳『アニー・ヴェ・アター』(Alan Flashman訳, the Bialik Institute,Jerusalem 2013)を手に入れ、兎に角、難解な印象しかない最初のページを開いたとき、すぐにブーバーの言いたいことが僕の心に飛び込んできた。あたかも『我と汝』は、最初からヘブライ語で書かれていたかのように!この書物の発想は、中世ユダヤ人の聖書のヘブライ語文法「ディクドゥーク(דקדוק)」の考える「人称」感覚に始まると考えるならば、彼の難解な冒頭の主張も、僕に理解できる翻訳可能な言葉に見えてきたのである。
人間の言語は須く三つの「人称」の区別を認めるが、それについて文法学は数字の1人称(I)、2人称(You)、3人称(He/She)という呼び名で表すのに対して、中世ユダヤ人の古典的ヘブライ語文法学(ディクドゥーク)では、1人称(私)はבעדו מדבר「メダベル・ベアドー」と呼ぶ。それは「自分自身のために語るもの」という意味である。2人称(あなた)はנמצא「ニムツァ」または ,נוכח「ノハフ」と呼び、それは「そこに存在している」または「目前にいる存在」という意味である。そして3人称は נסתר「ニスタル」と呼ばれ、それは「隠されたもの」という意味であるから、「彼/彼女/それ」の意義は、その場所にいない人、そこでは目には見えない「隠されている存在」を指す人称ということになる。この様に、ヘブライ語文法の三つの人称の呼称には、それぞれに、存在認識のニュアンスが与えられている。
したがって、ブーバーが考える「わたし-あなた」と「わたし-それ(彼、彼女)」という根元語は、人称的に言えば、「私」という語り手の一人称の意識と切り離して、「あなた」2人称とか「彼」3人称とかの言葉は使えないという現実を示唆しているのである。つまり人間の言語表現は、須く何らかの人称表現を取らざるを得ないのだが、その「人称」という概念はバラバラに成立している概念ではなく、二つのペアの意識を持つ「関係」概念なのである。
例えば、父とブーバーが出会い、互いの顔を目前にして言葉をかわす状況は、1人称と2人称で会話する「我と汝」の対話状況と言えるのだが、ただ実際の二人の言葉は、文法的には、彼ら自身のために語る1人称(私)の意識を前提に、目の前にいる相手に「あなた」と呼びかけているので、2人称で目の前の相手のために話をしているようでも、その深層意識は、自分のために語る一人称の意識と切り離せるものではない。だから、二人は、それぞれ、自分の中にある人称意識の二重性(関係性)を意識しながら言語行為を行なっている。
同様に、もう一つの根元語ペア「われ-それ」も、突き詰めれば、自分のために語る1人称の「わたし」の意識を前提に、そこにはいない隠された存在を、3人称「それ、または彼/彼女」で思い出しながら語る言語表現であるから、この場合の語りも、自分のために語る「私」の意識から切り離されているわけではいない。「わたし-あなた」の中で起きるのと似たような二重性の意識が「わたし-それ」にもある。ただ二つの根元語ペアには、違いがあるともブーバーは考えている。
すなわち、ブーバーによれば、すべて〈あなた〉という言葉を口にする人は、「わたし-あなた」の根元語ペアの中の「私」意識も伴い、またすべて〈それ〉を口にする人は、「わたし-それ」の根元語ペアの中の「私」が土台にある。そして、この二つの「私」の意識は同じではない。なぜなら、人は「自分の全存在」をかけなければ「わたし-あなた」の根元語ペアを口にはできないのに対して、「わたし-それ」の根元語ペアを口にする人は、「自分の全存在בכל קיומו 」をかけていう必要はないからである(Alan Flashman 訳,p.14の妙訳;田口訳 p.6と参照比較せよ)。
確かに、父とブーバーは、安息日のディナーのキャンセルを巡って、大袈裟に言えば、ブーバーは全存在をかけて、父を引き留めようとし、父も全存在をかけて、それを振り切ったと言えなくもない。その対話の風景は、二つの個性の強い人格が互いに愛情を持って「わたし-あなた」の根元語ペアの中の「私」をぶつけ合い、それが別れの際のブーバーの涙となった。そんな根元的な言語「わたし-あなた」の出会いでもあったと言える。
他方、僕は、この二人の出会いの出来事を、三人称で「隠されたもの」として解説をしている。つまり「わたし-それ」の根元語ペアの中で語っている僕は、ブーバーによれば、自分の存在をかけて、この話を語り伝える必要はない。だからか、ブーバー著作集(みすず書房)の第1巻の月報「ブーバー先生との出会い」(縫田清二)の中にも、目にいっぱいの涙を溜めるブーバーの姿を報告する記事に目が止まり、人の老齢期とはそういうものなのだと、クールに一般論でまとめることもできる。だが同時に、二人の出会いについて、僕は、「私が汝と出会うのは、汝が私に向かいよってくるからである。だが、汝との直接的な関係の中へ歩み入るのは、この私の行為である。このように、関係とは、選ばれることであると同時に選ぶことであり、受動であると同時に能動である」(田口訳 p.17)という『我と汝』の一節に感情移入して、この二人の出来事をみることもできる。
イスラエルのブーバーを近くでよく知る弟子・友人にフーゴー・ベルグマン(ヘブライ大学の哲学教授・カント学者)がいる。彼は、『我と汝』を、対話の哲学として、社会と個人などリアルな世界そのものを巻き込む「関係の哲学」として理解する。つまり、ブーバーの我と汝の思想の意義は、三つの人称(私、あなた、彼/彼女/それ)は、内在的にバラバラな三つの文法概念ではない。その内在的な人称意識の関係性は、現実の話者たちの存在関係性にも影響を及ぼし、分断された現実も一つにする力を秘めている哲学でもあるという。
しかし、一体なぜ「我と汝」の考えにそのような力があると考えるのか? 一つには、すでに述べたように、ユダヤの伝統的なディクドゥークの人称用語は、単なる数字で区別された1人称、2人称、3人称というドライな文法用語ではなくて、それぞれの人称が抱えている存在形式の違いを意識した名付け(自分のために話す話者の人称、目の前にいる人の人称、その話者の目前には居ない、隠されている人の人称)となっている。なので、自ずとイスラエルに帰還しヘブライ語話者として生きるベルグマンもヘブライ語の人称の持つ存在感を感じざるを得ないのだろう。でも、人称は全ての人間の言語に付随しているから、この感覚は全人類に普遍的なものでもあるはずである。特定の人種や民族の特有の感覚ではない。ただヘブライ語聖書の伝統は、その人称の存在感に敏感な言語の伝統なのである。
ところで、ディクドゥークは、アリストテレス命題論に倣って、人間の言語は三つの部分(名詞、動詞、その他)に分けられると教える。それを踏まえて17世紀のスピノザは「すべてのヘブライ人の声は・・接続詞その他を除けば、名前の特性・性質を持つ」(『ヘブライ語文法綱要』第5章)という。これは、とりもなおさず、ヘブライ語の基礎は名前(名詞)にあるという立場の表明であり、また動詞も名詞であるという主張でもある。もちろん、このスピノザの主張をエチカの哲学と関連づけて説明しようとすると面倒な議論にもなる。なぜなら、生成と消滅から「存在」を考える人々には、「存在」と「時間」は密接に結びついていて「時間」抜きで「存在」を考えることはできないから、動詞こそが名詞の基礎であるべきで、動詞が名詞に含まれるなど、彼らには考えられない。
だが、聖書の言語の文法としてヘブライ語の「名前」を考えるなら、目の前にやってくる生き物に名前を与えたアダムの記事「人が呼ぶと、それはすべて、生き物の名となった」(創世記2:19)にあるように、ヘブライ人の名前は、「存在しないもの」を前提にはしていない。須く存在しているから名前で呼ぶという発想である。だからאתה の文字が「アター(あなた)」と発声されると、それは目の前にいる生きた存在へのセンチメントを込めた呼びかけの名前の響きを持つ。同様に אני「アニー」という声を耳にするだけで、人は、自分のために語る「存在」が目の前にいて、自分に呼びかけてきていると感じるというと、ちょっと大袈裟だろうか。
僕は、ヘブライ語の時間感覚の特殊性で思い出すのは名詞文の特殊性である。本来、文章は、存在の様子を述べるとき、主語と述語(動詞)を必要とし、それらが一つに結ばれるときに文章になる。ただヘブライ語動詞には、完了形(過去)と未完了形(未来)の区別はあるが、現在形がない。つまり、「今~である」を表現する時、普通に必要になる「~Aは、~B である」の「は」(Be 動詞の現在形に当たるもの)がない。聖書の言葉は、動詞抜きの名前だけで現存在(プレゼンス)を示すことになる。
例えば、創世記26:24は、英語では「I am the God of your father Abraham」(日本語では「私はあなたの父アブラハムの神である」)と訳されるが、ヘブライ語聖書の原文「アノヒー・エロヘイ・アブラハム・アビハー」には、「は」にあたるBe動詞の現在形(am)がない。つまり動詞のない I the God of Abraham your father が聖書の名詞文の感覚である。
中世ユダヤの文法学者は、動詞と名詞の違いを説明して、動詞には「時間」が含まれるが、名詞には「時間」(つまり過去と未来の区別)はないという。それで「~がある」「~がいる」と、今ここに存在する状態を人称代名詞なしで表現したい場合、ヘブライ語では存在詞を使う(יש「イェッシュ(在る)」もしくは אין「エイン(無い)」を用いる名詞文にする)。だから、文法定義的に、動詞がない名前だけの名詞文(A は B)に時制概念(直列的な時間感覚)はない。つまり、名詞文が表現するのは、時間を超えた実体と様態のプレゼンスの真実であり、あえていうなら、「永遠の今」のような現在の感覚がヘブライ語の名詞文である。例えば、ユダヤ人が朝の祈りで唱える申命記の一節「主は、我らの神であり、主は一つである」(アドナイ・エロヘイヌ、アドナイ・エハッド)は、まさに名詞文で、これはユダヤ人には永遠の信仰告白なのである。
このようにディクドゥークの名前と人称にまつわる感覚で、ブーバーの『我と汝』を読み直すと、確かに、フーゴー・ベルグマンの読み方は可能かもしれない。つまり「わたし-あなた」「わたし-それ」の根元語は、単なる内在的な一人一人の人称感覚にとどまらない。それは、存在の関係性の哲学へと、さらには言葉を通して世界を再構築する対話哲学となる。そのことを、ベルグマンは、以下のブーバーのルーアッハ(風・空気/精神・霊を意味するヘブライ語)の比喩に代弁させる。
精神(息)は、その〈私〉というものの中にはない。それは、その〈私〉と、その〈あなた〉の間にあるのである。それは、あなたの中を流れる血液のようではなく、むしろ、あなたが息をする空気の様に、あるのである。もしも(人が)その自分の「あなた」に回帰する(תשובה/テシュバー)ことで答えることを知っているなら、人は精神の中で生きている。もし彼の本質の全部をもって「関係」の中に突入するのなら、その人はそのテシュバーで答えることを知っているのである。その彼の関係の力のみによって、人は精神の中で生きることが可能になるのである。(『ホゲイ・ハドール』p.180:『我と汝』田口訳p.52-3と比較せよ)。
父を戸口に立って別れを惜しみ見送るブーバー。改めて、その彼の泣いている姿の写真をみる。この一枚は、文字になった彼の言葉の精査以上に、ブーバーの二つの根元語ペアの話の雄弁なコメンタリーになっている(のではないかと、僕は、今思う)。確かに、僕も(多分、あなたも)別れよりも出会いを、断絶よりも対話を好む心を、一つになりたい気持ちを、持っているのではないか。僕らは、神の被造物だと思う。(了)
◆プロフィール◆
手島 勲矢(てしま いざや)
京都大学文学部非常勤講師。熊本県生まれ。1983年、エルサレム・ヘブライ大学卒業(聖書学科・ユダヤ思想学科 /B.A.)、1997年、ハーバード大学大学院近東言語文明学部・博士課程修了(聖書解釈の歴史 /Ph. D.)。単著では岩波書店『ユダヤの聖書解釈』2009年、共著ではPHP新書『原理主義から世界の動きが見える』2006年など。京都ユダヤ思想学会会員。元同志社大学神学部教授。
(『CANDANA』294号より)