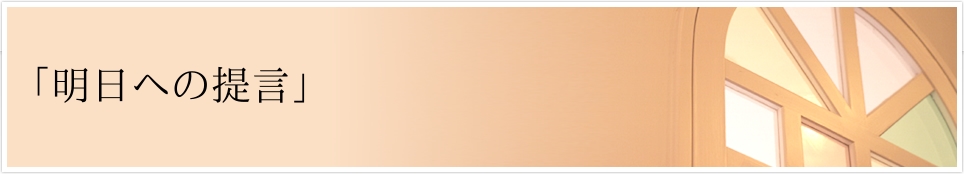荒牧小百合(洗足学園音楽大学/聖徳大学講師)
はじめに
音楽には不思議な力があります。
戦争や事故などで心の傷を負った人々の、カウンセラーの言葉でも癒えない傷でさえ、音楽を聴くと慰められたり癒されたり元気づけられたりすることがあります。また、音楽療法がガンなどの治療に直接使われるわけではありませんが、精神的な、傷以外の身体的な治癒力を高めたりすることが分かっています。
音楽療法は、古い時代から似たようなことが行われていましたが、第二次世界大戦後、アメリカの退役軍人の心のケアにおいて改めて音楽の癒しの力が注目されて発展していったようです。まだ比較的新しいこの分野は、これからも研究が進んでいくため、その効果は未知数ともいえるでしょう。
私たちが普段耳にする「音楽療法」の多くは、患者さんが施設内のホールなどに集まって生で演奏を聴いたり、一緒に歌ったり、体を動かしたりというスタイルです。音楽は楽しい時間を過ごして気分を明るくするだけでなく、予想もしていなかった成果を得ることができると研究でわかっています。たとえば、重度の認知症の患者さんで記憶力が大幅に低下しているかたが、音楽を流すと、5番まであるような童謡や唱歌の歌詞を完全に思い出して間違えることなく歌うことができたり、病により動かなくなってきたほうの手が音楽に合わせて動き始めたり、無表情であまり反応のないご高齢のかたが笑顔になったり、リハビリをする時に躍動感のある音楽が流れると、楽に感じられたりします。読者のなかでも、懐かしい音楽を聴いた時に、すっかり忘れていた昔の記憶が鮮明に思い出される体験をした人は少なくないでしょう。これらは音楽の不思議な力が作用した現象のほんの一部ですが、認知症や身体的にリハビリを必要とするなど、重度の症状をお持ちの患者さんにとっては、その進行を遅らせるなど、治癒への大きな希望となります。
音楽療法には生演奏の他、CD などの機械から流れる音楽を使った療法でも研究が進んでおり、多くの効果が発表されています。酷い痛みや気持ちが沈みがちな患者さんの心を和らげたり、病気による脳の損傷で不自由になった手足や言語のリハビリに使われたりします。
このような方法以外でもさまざまな種類の音楽療法があり、それぞれが高い効果をあげるなか、演奏家である私が注目したいのは生演奏で行う療法についてです。今回はさらに一歩進んで、患者さんの目の前で、そのかたのためだけに演奏される音楽の作用、また同じ空間にいる医療スタッフや家族に与える影響についても考えていこうと思います。
クレール・オペール氏の活動を通じて~音楽療法の未知なる可能性~
2023年初秋フランス大使館から、チェロ奏者で音楽療法士であるクレール・オペール氏との対談のお話をいただきました。チェロを奏でる音楽療法の記録が書かれた彼女の著書が日本語に翻訳されたので、その出版にあたり、日本のいくつかの学会で研究発表が予定されていました。大使館でもこの機会に著者を招き、全国で対談のイベントを企画したのです。私は音楽療法の専門家ではないので、他の適任のかたにお譲りして、当日は対談を聞きに伺いたいとお返事したところ、演奏家の立場で対談してほしいということと、二人でぜひ一緒に演奏もして欲しいというご要望でした。私としてもそれは非常に嬉しく、貴重な機会だとも思ったのでお受けすることにいたしました。そして早速、出版社から送っていただいた原稿を読み始めました。
『シューベルトの手当て』というその本は、療法士としての冷静な観察と、医師や看護師が協力して根気よく綿密に集めたデータ、そして音楽家の視点でそれらを捉えている点で、私にとって興味深い内容でした。また芸術家の優しい眼差しと、鋭く透明感のある感性が文章にもよく現れていて、表現や言い回しは読み物としても、非常に魅力的な本でした。
オペール氏が奏でるチェロの響きは、重度の自閉症のかたとコミュニケーションを取ることに成功し、認知症のかたの記憶を呼び覚まし、終末期の患者さんの心と体の痛みを緩和させました。そして音の調べは、付き添っているご家族や治療を施す医療スタッフの心にも優しく届いて癒しとなることが証明されました。
当初はチェロを弾くことだけで現場に関わっていたオペール氏でしたが、その後必要を実感して医学部で専門的に勉強し、様々な事例を理論的にデータ化して分析を行いました。この研究の成果が、医療スタッフと連携する効果的な治療に繋がっていったことは想像に難くありません。芸術と医療両方の知識と技術を併せ持った専門家はまさに理想的です。音楽によって患者さんの痛みが緩和されリラックスすると、医療スタッフは治療がしやすくなり、患者さんにとって、最も大切である心の安らぎを得ることができます。尊厳ある最期を迎えられることに音楽療法は貢献しているのです。
オペール氏の著書に添えられている文章と本文から少しご紹介します。
「10分間のシューベルト=5ミリグラムのオキシノーム(モルヒネ)」(緩和ケア担当医の証言)
2012年4月、パリの認知症患者のための老人ホーム。ある入居者が、包帯の交換の際に痛みで悲鳴を上げていた。
なんとかしようと看護師たちが格闘していた。ところがクレールがシューベルトを弾きはじめると、患者は急に静かに――。
老人はその後も、クレールのチェロ演奏があるときに限ってつらい処置を受け入れるようになった。音楽が痛みを和らげ、症状を緩和したのである。この本は自閉症患者や認知症患者などの前で音楽を奏でてきた希有な人物の物語だ。
(『シューベルトの手当て』の説明文より)
・ 患者の痛みは10~50%軽減し、不安解消のプラス効果は90%近く、看護師への好影響は100%
・ 重度の自閉症患者たちとの驚くべきコミュニケーション
オペール氏が大切にしているのは、その人のためだけの生の演奏です。どの施設においても、患者さんと一対一で音楽による対話を行います。すでに意識がなくなった患者さんの個室でチェロを弾き始めた時、その患者さんの呼吸が次第に深くなり、胸が大きく波打ったと書かれていました。身体の色々な機能が失われても、耳は最後まで聞こえて反応するそうです。
対談に先立ち、オペール氏が東京都立駒込病院のホスピス病棟と外来でコンサートを行うと聞き、見学させてもらいました。
当初ホスピス病棟では、個室を訪れて演奏する彼女のスタイルで行う予定でしたが、時間の関係で限られた人しか演奏を聴けないのは残念だという声が多く上がったため、ホールに集まって演奏を聴くことになりました。
時間が近づくと、それぞれのお部屋から、看護師に車椅子やベッドを押されて患者さんたちが集まってきました。
それはとても静かな時間でした。オペール氏が皆さんにあいさつをしてチェロを奏で始めました。しばらくすると、ベッドに横になっているかたの手がゆっくり持ち上がり、何かを伝えるような動きをし始めました。その他にも、目を開けたり閉じたりして気持ちを表現しようとしているかたも見受けられました。大きな拍手はなくても、その場にいる人たちが皆、チェロの音に耳を澄まし、体全体で音楽を感じているようでした。
この日は演奏のなかで静かに息を引き取るかたがいらっしゃいました。最期のときに音楽の翼に乗って旅立たれたかた、そしてそばにいたご家族にとっても癒しと慰めとなりました。オペール氏は、チェロを弾きながらその様子を感じていたそうです。
ホスピス病棟でのミニコンサートの後は、病院1階の外来受付のフロアで2回目のコンサートが行われました。次第に集まる患者さんや付き添いのかた、入院しているかた、病院スタッフたちでフロアはいっぱいでした。特に印象的だったのは、たくさんの医療スタッフと、熱心に聴き入る彼らの様子でした。忙しい診察の合間を縫ってその場に駆けつけた姿が、砂漠で水を求める人のように、チェロの音色を心から求めているように私には見えたのです。ある医師は、「今日のこの時間を本当に楽しみに待っていたのです」と熱を込めて私に話してくださいました。
オペール氏の本のなかにも、医療スタッフの声が紹介されています。チェロが奏でられると、いつもよりも楽に仕事をすることができたことや大きな声を張り上げなくなったこと、そして何よりも、看護の動作もより落ち着いて、やさしくなったという感想でした。そして体験した人の全てが、音楽による療法は有効だと答えています。
生の演奏の素晴らしいところは、演奏者の呼吸感も伝えられることです。先にも書きましたが、チェロの響きに導かれるようにして、意識のない患者さんの胸が少しずつ波打ち、深く呼吸し始めることが確認されています。また同時に、演奏の音は空気の振動で聴く人に伝わるため、耳だけでなく、皮膚全体で受け取ることができます。「音楽をきく」とき、イタリア語では「聞くascoltare」ではなく「感じる sentire」の動詞を使います。目の前で奏でられる音楽は空気の振動を通して体内の水や骨に伝わり、感じることができるのです。
今まで症状が重度の患者さんの話を取り上げてきましたが、軽度の患者さんにとっても、好みの曲や聴きたい曲を演奏してもらうことは大きな楽しみや喜びになります。演奏者にとっても、目の前の患者さんの様子を見ながら演奏の仕方や曲を選ぶことができるので、その時々の必要に応じて柔軟に最適な方法を取ることができるのはとても理想的です。
ヴェルディの家
イタリアのミラノに「ヴェルディの家(Casa Verdi)」という高齢者施設があります。「音楽家が、引退後も生涯音楽的な生活ができるように」という作曲家ヴェルディの願いを込めて1902年に設立された「音楽家のための憩いの家」として作られたのです。
オペラ演出家でもあるダニエル・シュミット監督が、この「ヴェルディの家」に住む、往年のオペラ歌手やバレリーナたちを取材したドキュメンタリー映画『トスカの接吻(IL BACIO DI TOSCA)』を1984年に発表しました。これは、彼らが昔を思い出しながらオペラを歌い演じる姿を捉え、芸術の永遠性を訴える作品です。この作品のなかで、いくつもの印象的なシーンが出てくるのですが、共通しているのは、長い年月を隔て、どんなに歳をとって体が不自由になっても、かつて歌い慣れ、踊り慣れた音楽が流れると、思いがけず体が反応して動き出し、歌声が溢れ出るということです。私はこの映画を観て、音楽の不思議な力が彼らを突き動かしているように感じました。
この「ヴェルディの家」では、高齢者の他に、コンセルヴァトワール(音楽学校)の学生たちも住んでいるのがもう一つの特徴といえましょう。学生たちはここでコンサートを開いたり、豊かな経験と知識を持つ老芸術家たちからアドバイスやレッスンを受けたり、人生についても相談することができます。若い彼らにとってまたとない学びの環境になるだけでなく、高齢者たちにとっても、自らの経験が生かされ必要とされることで生き甲斐を感じるとともに、未来ある若い人たちの成長を見守れる喜びがあります。これは音楽を通じた交流が人生を豊かにする素晴らしい例です。
音楽療法におけるモーツァルト効果
音楽療法の分野では有名な「モーツァルト効果(The Mozart effect)」の研究が報告されています。フランスの耳鼻科医、アルフレッド・トマティスの著書『モーツァルトを科学する~心とからだをいやす偉大な音楽の秘密に迫る』のなかで、高周波音を多く含むモーツァルトの音楽には様々な効果があるというのです。その効果は、以下の11個とされています。
①日々の生活のなかで創造力や想像力を育てる作用があること
②会話におけるヒアリング能力を高めること
③不安やストレスを減少させる作用があること
④記憶力を高め、認知症を改善させること
⑤ 精神的な安心感を誘導し、幸福感を高めること
⑥心臓の作用を安定化させ、心拍の安定化を図ること
⑦血圧を安定させること
⑧脳波をリラックス状態に導き、アルファ波を引き起こすこと
⑨ストレスホルモンを減少させる作用があること
⑩免疫力を高め、健康に導くこと
⑪エンドルフィンの分泌を促し痛みの緩和効果をもたらすこと
そして音楽によって変化するのは人間だけではないようです。モーツァルトの音楽を犬や猫といったペットに聞かせることで、心理状態を落ち着かせてリラックスさせる効果があることが近年の研究でわかってきました。牛舎でモーツァルトの音楽を流すとホルスタインのミルクの出が良くなったり、植物に音楽を聞かせると光合成が活発になり成長が促進されたり、トマトの甘みが増したり、発酵食品の味噌や日本酒の熟成が早まったりしたという結果も報告されています。また、ハーバード大学の実験において、生体臓器移植をしたマウスは7日間しか生きられないけれど、モーツァルトの音楽を聞かせると、平均20日間生きられるようになったそうです。
オペール氏が明らかにした数多くの音楽療法の結果と照らし合わせたとき、音楽を耳で聴くだけでなく体全体で感じて脳にも影響を与えることが証明されています。ですから聴覚器官を持たない植物や微生物、また聴覚に障がいを持つかたも音楽を享受することができるのです。人間も動植物や微生物も体内の70~90%が水でできています。その細胞内の水環境に高周波音が振動として作用して影響を受けるわけです。これは自然のなかに存在する様々な音、鳥のさえずりや虫の音、川のせせらぎや風が木の葉をゆする音のなかにも、耳には聞こえなくても高周波音は存在していて、それを感じることで気持ちが安らいだりリフレッシュしたりできるのと同じ効果です。
CD やデジタル放送などの機械では、「聞こえない音は不要なもの」と判断されて、残念ながら高周波音が大幅にカットされていますが、自然の音や生演奏のなかではそれが豊かにあって、たとえ耳で聞こえなくても、皮膚で感じることができるのです。そして音楽には薬のような副作用はなく、体の痛みとともに心も癒され、明るく穏やかな気持ちにしてくれる魔法ともいえる良薬です。
音楽療法を効果的に用いることにより、不思議な力が作用して、全ての患者さんが心穏やかに、最期の時までその人らしい尊厳ある人生を送ることができることを心から願います。
〈参考文献〉
クレール・オペール(Claire Opperr)著/ 鳥取 絹子 訳『シューベルトの手当て(Le Pansement Schubert)』(アルデスパブリッシング 2023年)
アルフレッド・トマティス(Alfred Tomatis)著/窪川英水 訳『モーツァルトを科学する~心とからだをいやす偉大な音楽の秘密に迫る(Pourquoi Mozart)』(日本実業出版社 1994年)
村井靖児著『音楽療法の基礎』(音楽之友社 1995年)
村井靖児著『音楽療法を語る~精神医学から見た音と心の関係~』(聖徳大学出版会 2004年)
野田 燎/後藤幸生 共著『脳は甦る~音楽運動療法による甦生リハビリ』(大修館書店 2000年)
久保田牧子 著『歌声が心に響くとき~音楽療法との出会い~』(悠飛社 2002年)
スーザン・マンロー(Susan Munro)著/ 進士和恵 訳『ホスピスと緩和ケアにおける音楽療法(Music therapy in palliative/Hospice care)』(音楽之友社 1999年)
◆プロフィール◆
荒牧小百合(あらまきさゆり)
熊本県生まれ。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業、同大学院修士課程修了。洗足学園音楽大学非常勤講師、聖徳大学講師。日本声楽アカデミー会員。
2019年ウィーンで開催された日墺修好150周年記念公演にてE.オルトナー指揮のモーツァルト「レクイエム」でソプラノソロを務めた。外務省認定事業「2018-2019ロシアにおける日本年」では3度にわたってロシアに赴き、モスクワや近郊都市で数々の演奏会に出演した他、ギーチス演劇大学オペラ科で「日本の歌」のワークショップを開催。この他スイス、クロアチア、スロヴェニアでも演奏の機会を得ている。オペラチックナイトを主宰し、これまでに《椿姫》《アイーダ》《蝶々夫人》《トスカ》《カヴァレリア・ルスティカーナ》をプロデュース及び主演を務める。趣向を凝らした舞台は、オペラを初めて観る人から好評を博している。
(『CANDANA』301号より)